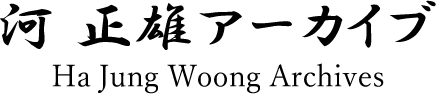「伝説の舞姫」
舞踊家・崔承喜(チェスンヒ)(一九一一~一九六九)
〈接点〉
光州市立美術館創立一〇周年記念河正雄コレクション『伝説の舞姫・崔承喜写真展』を、二〇〇二年八月一日~一〇月二〇日まで開催することとなった。
崔承喜(一九一一~一九六九)は、朝鮮が生んだ(植民地時代は日本が生んだと言われていた)世界舞踊史上に咲いた唯一無二の華、東洋の心を踊る新しきルネッサンスをもたらした天才的かつユニークな舞姫である。
崔承喜の名は、私の故郷である秋田でも知られており、私自身幼い時から誇らしく聞いて育った。それは、崔承喜が秋田出身の石井漠の門下で学んだからだ。私が生まれた年の一九三九年、六月二四日に秋田市で渡欧告別公演、翌一九四〇年八月一六日には帰朝公演が開かれ、その記憶が秋田の人々に鮮烈に残っていたからだと思う。
崔承喜の解放(終戦)後にまつわるエピソードは東西の冷戦、韓日、朝日との歴史的な関係により運命を歪められ、悲劇に彩られている。不幸な歴史に翻弄されたその姿は、在日に生きる私には共感と哀感を抱かずにはいられない、愛おしき人物の一人である。彼女の名誉のため、誇りのためにも、彼女が生きた時代とその足跡を検証してみる必要があると思うのは、同時代を生きた我々の名誉のため、誇りのためでもある。
崔承喜については、日本の著名な文士や画家、彫刻家が記したメモリアルが数多く残されている。この写真展にこぎつけるまでの、崔承喜に寄せた私の想い〈在日〉の心の軌跡や動機の一端を綴る。
〈出会い〉
今から四〇年以上前で一九六〇年代のことになるが、私は画家になる青雲の志を抱き、絵筆を握っていた。その頃、埼玉県大宮市(現在のさいたま市)の宮町に山水園という焼肉屋が開店し、私はその祝いに招待された。店の造りは韓国風のインテリアで、とても凝っていた。店主の林清哲(故人)氏が
「河さん、この店には絵が一枚もないので淋しい。何か、民族的な雰囲気の絵を描いてもらえないだろうか」
と頼まれた。当時、焼肉店で油絵を飾るというのは珍しく、無名の私に依頼されたのに驚かされた。私はその時、朝鮮画報に載っていた崔承喜の写真から『杖鼓の舞』を描くことを約束した。一〇号の作品を書き上げたところ、林氏はとても気に入ってくれたようで
「五万円の画料を払いたいが、開店したばかりなので申し訳ないが三万円で勘弁してくれ」
と言って三万円をくれた。当時の私の月の収入は一万円、無名の私には破格の画料であった。これでしっかり勉強して、将来名のある画家になれと言う励ましだと受け取り、その心遣いを有り難く思った。それにも増して、認められた喜びは私に大きな力を与えた。
私のコレクションの中には、崔承喜を描いた油絵二点と版画二点がある。新大久保駅近くにある〈チロル〉というカラオケスナックで、私はよく遊んだ。ママは友人であり、尊敬する白玉仙さん。
一九八〇年代後半のことである。〈チロル〉店内の壁面に、一枚の絵が無造作に掛けられていた。煙草の煙で燻されたのか薄汚れ、照明を落とした店内では、その絵がよく見えなかった。長い間別に何ら気に留めてなかったものだが、ある時、近づいてよく見てみた。チョゴリを着て長鼓を持った、上半身の舞姿の絵であった。その絵は一〇号の油絵で、一九六〇年代に私が描いた崔承喜の『杖鼓の舞』と構図(私の絵は全身画)がそれとなく似通っていた。
「白さん、この絵を譲って下さい」と申し入れたところ、
「ええ、いいわよ」
といとも簡単に承諾してくれた。汚れを落としサインを見たところ、ハングルで〈キム・チャンドク一九六七〉と記されていた。それは一九六〇年代、私が所属していた文芸同(在日朝鮮文芸芸術家同盟)の美術部長金昌徳(日本名・高橋進 一九一〇~一九八三)が、崔承喜の『長鼓舞』を描いた作品であったのだ。偶然でなく必然とも言える出会いを、強く感じる絵であった。
もう一枚の油絵は宋英玉(一九一七~一九九九)の作品である。晩年、白内障で苦しんでいた宋英玉は、娘さんに伴われて我が家をよく訪ねて来た。後年、白内障の手術が成功し元気になったと快気の礼にと持参したのが、崔承喜の『長鼓舞』(一九八一年作)の絵であった。その絵は金昌徳の『長鼓舞』の構図に似通っていた。どちらも上半身の長鼓舞を描いたものだが、顔の向きが左右に違うなど微妙に異なる構図であった。崔承喜に想いを寄せ、憧憬の念を持って描かれた作品なのだろう。宋英玉の重く沈静した画風にしては珍しく、華やいだ色彩であり救われるような明るい作品だった。
版画は松田黎光(一八九八~一九四一-本名・正雄)の一九四〇年作、『僧舞』と『剣舞』の二点である。鮮展参与となり、帝展・文展にも出展し、江西双楹塚(こうせいそうようつか)壁画の模写を成し、国民総力朝鮮美術家協会理事であった、鮮展初期以来の作家である。この年代、称賛を浴びていた崔承喜を、安井曽太郎、小磯良平、梅原龍三郎、東郷青児、有島生馬、鏑木清方らが競って描いた。黎光も、崔承喜をモデルにしてこの作品を制作したものと判断し、私はこの絵をコレクションした。
〈メキシコの旅〉
私は、シケイロスと交遊のあった北川民次の絵が好きだった。
一九九八年、私は妻とメキシコ旅行に出掛けた。古代メキシコ文明、アステカ・マヤ文明の遺跡に興味もあったが、北川民次の画風に影響を与えたシケイロスの壁画を見たかったからだ。巨匠シケイロスは一九一三年、メキシコ革命に参加した。ヨーロッパの現代美術とメキシコの土俗的な伝統を結合させ、国民(民族)的芸術を主張し、力強い社会的表現をしたメキシコの画家である。
私はメキシコシティのアラメダ公園東端にある国立芸術院を訪ねた。白大理石の建物の外観は、ネオクラシックとアール・ヌーボー、内部はアール・デコ様式の折衷様式であり、一九三四年に完成したものである。二階と三階の壁面にあるシケイロスの巨大で力強い作品に出会ったときは、息を呑むような感動を受けた。そこにはメキシコを代表する世界的な画家、タマヨ、リベラ、オロスコらの作品も展示されており、思いもかけぬ数々の作品との出会いを喜んだ。
案内をしてくれた同院の学芸員に、私は日本から来た韓国人だと挨拶したところ
「この建物には三五〇〇人収容の劇場がある。一九四〇年には崔承喜の公演があった」
と紹介された。そのとき時空を超え、クラシカルで絢爛たるその劇場で民族の舞を踊っている崔承喜を想い描いただけで、熱いものがこみ上げてきた。異郷のメキシコ人が崔承喜を知っていた、忘れないでいてくれたというだけで感激してしまった。メキシコの旅は、思いがけず崔承喜の足跡を訪ねる印象深いものとなった。
〈鄭昞浩先生〉
一九九七年、在日韓国人文化芸術協会主催の文芸協講座に崔承喜の研究者である韓国中央大学校名誉教授の鄭昞浩先生をお招きし、『崔承喜の芸術と生涯』の講演をして頂いた。このことが御縁となり後日、先生が収集された崔承喜に関するスライドフィルムを拝見する機会を得た。膨大なスライドを見せていただいた後に、私は
「先生、このフィルムを譲って頂けませんか?私の記念室がある光州市立美術館で、崔承喜の足跡を写真作品にして展示したい」
と申し入れた。しかし先生は関心を持たれなかったのか、そのときは承諾して下さらなかった。
その後、一九九九年白香珠の舞踊公演の際に、奥様と共に来日したとの連絡があり、東京で会うこととなった。そこで
「崔承喜の存在と足跡を知らしめたいという、河さんの申し入れの意図と主旨がわかった。フィルムのコレクションをあなたに譲りましょう」
と言われた。私は諦め忘れていた事柄が思いもよらず叶ったことに、先生の理解に感謝し喜んだ。
こうして、山口卓治氏紹介によるサカタラボステーション株式会社の協賛で、そのフィルム資料をパネル作品として製作することが出来た。古い時代の、原版からコピーされたと思われる三五ミリフィルムからのパネル化は困難を極めた。費用も嵩んだが、一点一点修正しながらの手作業で最善を尽くしていただいたパネルは、良い作品に仕上った。ソウルの演出家鄭秀雄氏は写真を提供下さり、鄭昞浩先生は写真解説と年譜、そして写真フィルムを寄贈するにあたり、その動機を記した文を寄せて下さった。
鄭先生は、韓国が一九八七年に越北芸術家の復権措置が執られる以前から、韓国を代表する崔承喜研究の第一人者である。一九九五年には秀作『踊る崔承喜』を出版された。長年かかって集められた崔承喜の史料や資料、記事、写真などのコレクションは貴重なもので、その業績が評価されている。「伝説の舞姫・崔承喜写真展」開催が成されることとなったのは、鄭先生の寛大なるご理解とご指導のおかげである。この紙面を借りて、敬意と感謝の意を表する。
また資料収集にあたり、国会図書館総務部長・大滝則忠、アジア資料課の富窪高志、文化センターアリランの幸野保典、秋田さきがけ新報社の佐川博之、各氏の御協力ご尽力を頂いた。わらび座の茶谷十六氏は、愛蔵のプロマイドを数点寄贈して下さった。心から感謝申し上げたい。
〈芸術はイデオロギーを越える〉
二〇〇三年二月九日、朝鮮中央通信が「祖国の光復と富強繁栄のための聖なる偉業に尽くした二二人の烈士の遺骸が、愛国烈士陵に新たに安置された」として、それまで粛正説が流れ、生死不明であった崔承喜の名を伝えた。崔承喜が、北朝鮮で三四年ぶりに名誉回復されたのである。最近、一緒に失脚した崔承喜の娘、安聖姫の墓の所在も、近い内にはっきりするだろうとの話も出ているようだ。
芸術はイデオロギーを超える。崔承喜が世界的な芸術家であることを認識することが、我々にとって有意義なことである。崔承喜の世界同胞主義を理解し、植民地時代、あの苦しい時代を生きた我々朝鮮人の自尊心を団結させてくれた崔承喜を、今日的に再評価するべきであると、鄭昞浩先生は熱く語った。崔承喜の芸術的活動の足跡と、彼女が生きた時代と民族史を知ることは、現在に生きる我々にとっても重要であると思う。崔承喜を知らない若者達に、未来に誇りと夢を育む写真展になることを祈念してやまない。
『舞姫・崔承喜写真展』を見て
横江文憲(東京都庭園美術館学芸係長・写真史)
写真が持つ重要な機能の一つとして〈記録性〉を挙げることが出来るが、この展覧会ほど、そのことを強く感じたことはなかった。また〈伝達〉という意味においても、時代を超え時を越えて多くの人々に訴える力を認識させられた。
韓国の光州市立美術館で、今年八月から一〇月にかけて『舞姫・崔承喜写真展』が開催され、同館名誉館長の河正雄氏に紹介されて見る機会を持った。崔承喜は私にとって、戦前の日本で活躍した世界的な舞踏家であり、著名な画家や写真家がこぞってモデルにして作品を残しているという知識しか持ち合わせず、それまで彼女の写真を見たという記憶はなかった。
展覧会の会場に足を踏み入れて圧倒された。崔承喜の肉体が宙を舞い、その表現力の容易でないことを瞬間に感得することができた。彼女の均整のとれた肉体、そこから溢れ出る躍動的なリズムは、観る者を彼女の舞踏の世界へ誘う。また、同時に展示されている夥しい数の印刷物やアルバム、油絵等の資料は、一九二〇年代から一九六〇年代に活躍した天才的な舞姫崔承喜を立体的に浮かび上がらせている。
昭和一〇年頃、崔承喜の人気は絶頂にあり、恩師石井漠は、
「彼女の一挙手一投足は、通常の人間の二倍の効果をあげることができる」
と言い、川端康成は、
「他の誰を日本一というよりも、崔承喜を日本一と云いやすい。第一に立派な体である。彼女の踊りの大きさである。力である。それに踊りざかりの年齢である。また彼女一人に、いちじるしい民族の匂いである」
と書いている。さらに村山知義は、
「日本的なるものの母の、母の、その又母のいぶきを感じることが出来た」
と述べている。これらのことだけみても、崔承喜の日本国内における関心の高さを窺い知ることができる。しかし、文字だけでは、想像することはできても、実感として伝わってこない。写真は、それを映像として如実に提示することができる。
崔承喜の存在の重要さは、そのことよりも遥かに高い次元にあり、まさに波乱万丈な人生を歩んだことを教えてくれた。
「韓国現代舞踏の先駆者であると、日本帝国植民地時代の韓国を代表する舞踏家として、世界の舞台で活躍し、国を失った韓国民に慰安と希望とをあたえてくれるとともに、深い祖国愛を呼び起こした舞踏家崔承喜」(※1)「韓国舞踏家として世界的に名声を馳せ、全盛期に北朝鮮へと越境したが、最後には粛清されたことにより様々な逸話を残した」(※2)と書かれているように、韓国に生まれ、日本から羽ばたき、北朝鮮で消息を絶った数奇な運命であったがために、近年まで彼女の研究をすることができなかったのである。
今回の展示は、一九八八年に越北芸術家たちに対する解禁措置がとられてからの研究成果である。写真フィルムは、中央大学校鄭昞浩名誉教授が収集したものであり、展示物の殆どはそれを河正雄名誉館長が形にした。調査研究というレベルでの文化交流は端緒についたばかりであり、今後、日韓両国の重要な課題であろう。(※1、2は展覧会カタログより)
「天上の弦・在日の虹」
バイオリン製作家・陳昌鉉(チンチャンヒョン)(一九二九~ )
〈陳昌鉉氏との出会い〉
陳昌鉉氏との出会いは一九八二年、在日韓国人文化芸術協会(文芸協)創立総会の時である。その時、在日には文化がない、このような協会が出来ることを待ち望んでいたと陳昌鉉氏は喜んでいた。
私は二〇代(一九六〇年代)からの『リーダーズ・ダイジェスト』の愛読者であった。七三年、同誌に『東洋のストラディバリウス』と陳昌鉉氏が紹介されていた。在日一世が世界で読まれている雑誌で認められ、紹介されていた事を、自分まで誇らしく感じた。これが陳昌鉉氏との御縁の始まりであるともいえる。私は今もその本を大切に保管しているが、その後に続いた文芸協の行事等でお会いして、その都度、在日の文化についての熱い想いを聞き、尊敬の念を抱いていた。しかし日本社会や文芸協の間では、陳昌鉉氏の名声や名誉について、どの程度のものかという特別な評価や話題にもならず、本人自身も静かに身を処していた。私には、その状態がもどかしい感情を長い間抱いていた。
〈光州市立美術館に寄贈〉
一九九三年、私が光州市立美術館に美術品を寄贈するニュースを知った陳昌鉉氏は
「在日の快挙だ、誇りである」
と祝意を表してくれた。その後、私は一九九九年に第二次、二〇〇三年に第三次と寄贈を続けていった。私は寄贈に当たり光州市に対し、何の条件も付けていなかった。そこで市側から、何か条件、要望はないかと問い合わせがあった。
「それならば、無名ではあるが将来有望なる青年作家を育てる事業を、青年作家招待展として行ってはどうか」と提案したところ、光州市立美術館のメイン行事の一つとし、私の誕生月の一一月に毎年の恒例行事として開催することとなったのである。
私は陳昌鉉氏に、その経緯を伝えた。すると
「私は在日二世としての勇志と、祖国に対する奉仕精神に共感している。私もあなたと同じ夢と希望を持って、前途ある青年作家達を育ててみたい。私は慶北出身であるが、日本が第二の故郷なら光州は私の第三の故郷。在日のイメージとして光州に永遠に残るでしょう。私のヴァイオリンを作品として、河正雄コレクションに寄贈しましょう」
と意表をつく申し入れをされた。コレクションの内容と質の向上という意味で、非常にありがたく思った。美術館側から、ヴァイオリンが美術品になるのかという物議が挙がったが、超一流の作品であることが認識された。
二〇〇一年、第一回河正雄青年作家招待展は、寄贈された東洋のストラディヴァリウスの名器が奏でるサラサーテ作曲『ツィゴイネルワイゼン』の演奏で開幕した。ドイツ語でジプシーの歌という『ツィゴイネルワイゼン』は、スペイン生まれの名ヴァイオリニストであるサラサーテ(一八四四~一九〇八)の代表作。陳昌鉉氏は、在日もある意味では自己の存在を捜す彷徨い人、ジプシーの血を持つ。エネルギーが湧くと、最も愛聴しているこの曲を選んだ。光州市立美術館でクラシックが奏でられ展覧会が開かれたのは、これが初めてのことで、集まった観客に音楽がもつ感動と、意義を伝える事が出来た。
そして陳昌鉉氏は翌二〇〇二年、ヴァイオリン、ビオラ、セロの計三点を追加寄贈して下さった。それらは第一ヴァイオリン光州号、第二ヴァイオリン大邱号、ビオラ漢拏号、セロ白頭号と命名された。寄贈された楽器による光州市立交響楽団の四重奏(カルテット)の演奏から始まる開幕式は、二〇〇四年一一月二三日に第四回を迎えた。この行事は光州市立美術館では定例化され、歴史を刻んでいくこととなった。
〈人生の岐路〉
ヴァイオリン作りの名工である陳昌鉉氏は、植民地下の一九二九年、韓国慶尚北道金泉郡梨川里で生まれた。一三歳の時に父を亡くし、家族は困窮していたため、中学進学を諦め、一四歳の時に生まれ故郷を離れ、母と別離した。腹違いの兄がいる福岡に渡り、旧制中学の夜間部に転入した。博多では進学するために、天秤棒で石炭を担いで船に運ぶ港湾労働。中学を出てからは神奈川、小田原の架橋工事現場や軍需工場で、日雇い労働に従事した。横浜に出て輪タク(人力車)を始め、学資を貯めた。そして教員を目指し、明治大学二部(夜学)の英文科で学んだ。しかし教員資格を取ったにも関わらず、当時日本国籍を持たないものは教員にはなれないという壁が、卒業間際になって立ち塞がった。
進路を見失っていた時に、日本ロケット開発の礎を築いた科学者・糸川英夫博士(一九一二~一九九八)の『ヴァイオリンの神秘』という講演を聞いた。その事が人生の岐路となった。
「音響物理学を駆使してストラディヴァリウスの音を分析し、同じ音色を再現できるであろうかと研究を重ねたが、現代科学の粋を集めても、その技術は解明出来ず、謎であり神秘である。ヴァイオリンの名器を再現することは、永遠に不可能である」
と、名器ストラディヴァリウスの製作研究論文の糸川博士の講演を聞いた瞬間、陳昌鉉氏は雷に打たれたような衝撃を受けたという。
形の美しさにおいても、作りの完璧さにおいても、他に比類のない逸品を残した天才。
ヴァイオリン製作の〈王の中の王〉。世界最高の価値を持つ弦楽器を作り出したイタリアのクレモナ、アントニオ・ストラディヴァリ(一六四四~一七三七)。名匠ストラディヴァリの卓越した腕は、頭部の彫りやf字孔の美しさ、そしてニスの美しさにあると言われる。その音色は力強く、透明感があり、明るく輝きがあって、一流の芸術品であると言われている。
「僕の進むべき道はこれだ。糸川博士をして匙を投げざるを得ない、不可能と言われた事を、僕が成し遂げてみせよう。凡人の僕が挑戦しても悔いる事はない」
と心に決めたという。人生を賭けた運命の始まりである。
小学生の頃、陳昌鉉氏の家に下宿していた相川喜久衛先生が、良くヴァイオリンで『荒城の月』『桜』を弾いて下さったという。大学に入り教員になろうとしたのも、相川先生のような先生になりたいという憧れがあったのだという。その音色に見せられ、弾き方を教えてもらったことが、そう決心する伏線にあったのであろう。ヴァイオリンは「fidlle」とも呼ばれ、人に魔力をかける、人を誑かすという語感を持つという。陳昌鉉氏は、その時、魔力にかかってしまったのである。
人間によって作られた物だから、必ず再現してみせると運命を決めた初心は非凡である。その野心は必ず名器を作るという信念で、その道を選んだ訳でもなく、面白いと思ったことを好奇心でやる以上は、人生を棒に振っても元々であるという楽天的なものであったのであろう。クラシック音楽の楽器作りという、閉ざされた世界に全くの徒手空拳で挑み
「前人未踏のヒマラヤの山々にも、そこに登ることの出来ない、厳しい氷壁があるからこそ、敢えて人は挑戦する。執拗に挑戦し続ければ必ず、その壁を克服できるものと信じる」
という青春の情熱そのものが、なにものにも変えがたい価値なのだ。
〈道を拓く〉
それから陳昌鉉氏は、ヴァイオリン製作のための弟子入り先を捜す行脚を始めた。しかし日本人の製作者に当たってみたが、決まって門前払いを喰らい、どこも受け入れてはくれなかった。アルバイトで食いつなぎながら二八歳になったときに、弟子入りを諦めた。朝鮮半島出身であるという辛酸を舐め、独学で学ぶしかなかったからだ。失敗や挫折の連続であったが、ストラディヴァリウスを越える夢に向かって、執念と努力するところに可能性が広がっていった。
そして行き着いた木曽福島で、電柱などを利用して丸太小屋を建て、そこをアトリエ(ヴァイオリン工房)とした。ヴァイオリン関係者が多く住む木曽福島は職人の町。伝統的な木工芸の町に、居を定めたことが後に繋がる。生活費は、川底から掬った砂利を売って稼いだ。その地域では変人扱いされながら、教えてくれる師匠もいないままに独学研究の日々を送った。人から学べない為に、自然から学ぶしかなかったのだ。風で揺れる枝の曲がり具合をヴァイオリンの曲線に生かす、創意工夫は木曽の自然の中から多くのものを学んだという。
ヴァイオリンの価値は音とニスの色にある。一人で本を読み漁り、素材となる木を熟知し、独自の色つやの出し方を修得した。新品でも一〇〇年以上も使ったような艶を出すために、ニスの素材を突き詰める実験を、未知の領域を手探りで試行錯誤しながら繰り返した。寿司屋の墨イカ、干したミミズの粉末や蝉の抜け殻、長男の便等、およそ考えつくもの全てをニスの原料にと試してみた。ミミズの鳴き声が、ストラディヴァリウスの最弱音に酷似していることを発見したのも偶然ではない。アフリカ大陸、インド、東南アジア、中南米等を放浪し、染料と樹脂を捜す旅から貴重な情報や資料を得ているのである。
近年になっても、染料を求めて、アマゾン上流のジャングルを一週間彷徨った。ヴァイオリン製作は勘や経験に頼る所が多く、論理的に出来るものではない。ヴァイオリン製作には公式が存在しない。自然を感じるままに感性を鍛え、研ぎ澄ます。感性を磨かなければ失われるものであり、努力なしでは維持向上を望むことは出来ないからだ。一%の可能性を求め、確信を持って一つのことを貫く。好奇心は可能性の出発点であり、能力を研ぎ澄ますことで道を拓くことが出来るのであるという。
〈東洋のストラバリウス〉
陳昌鉉氏のヴァイオリンは、音がクリアで鮮明にして柔らかく甘美である。フォルムも自然と一体感があり、温かみがあると定評を得ている。木曽の自然が、陳昌鉉氏の感性を育んだ出発点であることが、作品に自然と表れているといわれる。
一九六一年になって、完成させた四〇挺のヴァイオリンの中から、一〇挺を東京に売りに出掛けた。そして、そのヴァイオリンを全部買ってくれたヴァイオリニスト篠崎弘嗣氏に出会ったことで、大きく運命が動き始めたという。人との出会いが、人生を動かすエッセンスとなるのは、生きることの妙であろう。
薦められて出品した作品が、一九七六年フィラデルフィアでの〈国際ヴァイオリン・ビオラ・セロ製作者コンクール〉において全六部門中、五部門において金賞を受賞。一九八四年にはヴァイオリン製作者協会から、全世界に五人しかいない〈無鑑査マスターメーカー〉の称号を授与される栄冠に輝いた。苦境の運命を、弛まざる努力で克服したのである。
「名器と呼ばれる楽器には絶妙な部分があり、それは自然の摂理の妙にかなっている。だから私の作品を名器だとは思わない。名器とされる楽器は、自然の摂理に合致しているもので、法則で示すことが出来ないから、思い切った発想と努力で暗中模索するしかないのだ。ヴァイオリンは神秘に満ち、永遠に謎の楽器である。私にとってストラディヴァリウスこそが虹、天上の弦である。自分は山で例えるならば七合目、ストラディヴァリウス等の名器は、作者が八〇歳を過ぎた晩年に作られた物が多いので、私はまだ七五歳、これからです。何とか頂点を極めたいと思う」
陳昌鉉氏は、自らをそう評している。
〈海峡を渡るヴァイオリン〉
陳昌鉉氏の人間愛と波乱の人生を、SMAPの草彅剛主演でドラマ化したフジテレビ開局四五周年記念企画・文化芸術祭参加作品『海峡を渡るヴァイオリン』が放送された。真摯に己の道を貫いた陳昌鉉氏の人生が、草彅剛の熱演によって見事に演じられていた。
作品中、心に特に残った場面がある。オダギリジョー演じる相川先生が、滝廉太郎(一八七九~一九〇三)の『荒城の月』について、陳昌鉉少年に語る場面である。
「荒れた城に、美しい月が出ている情景を思い浮かべなさい」
「何故、城が荒れたのですか」
「勝っても負けても、戦争をすれば城は荒れる」
というくだりである。まさしく戦争と、それを起こす人間の愚行の悲しさを描いていると思う。それは、我々の〈恨〉の原風景でもあり、拭い去ることの出来ないイメージである。
在日というマイノリティーの環境にいたこと。マイノリティーであることをハンディとするのではなく、逆に弾みにして、不可能を可能にする力に変えて生きる道を捜す。試練というハードルを乗り越えようと、努力し続ければ天は力を貸してくれる。
「貧すれば鈍するという生き方は、私の哲学に反する。在日だからこそ、日本や韓国にない独自の研ぎ澄まされた感性がある。真似の出来ないものが認められていくことで、差別という壁を打ち崩していくことができるのではないだろうか。在日をマイナスの遺産と見るのは、余りに一面的すぎる。
我々が変わらなければ日本は変わらない。在日を取り巻く諸条件こそ、逆に在日の強みであり、源泉である。日本で韓国、朝鮮人として生きるのにも意味があり、日本を豊かにする無限の可能性さえ持っていると思う。私は日本に来たからこそ、平坦ではなかったが、好きな道を歩くことができた。運命が厳しかったからこそ、生きるために執念を燃やし、後ろ向きにならず、真剣に生きてきた。在日で生きるには、自分が日本社会に必要な人間であると思われるようにならなければならない。それには裏付けが必要であり、日本人、韓国人の何倍も努力して、それ以上の資質を持たねばならない。在日の存在を知らせ、見直してもらったことは幸せである」
陳昌鉉氏の人生は『在日だから』という訳でなく、志と夢を貫き通した艱難辛苦の人生から学ぶべき〈人間の価値〉がある。
〈陳先生の故郷を訪ねて〉
二〇〇五年八月二五日から二八日まで、憧れの木曽福島の町を訪問した。
第三一回木曽音楽祭のご案内を、陳先生から頂いたのがご縁である。実は二〇数年前から、木曽福島が陳先生の第二の故郷と聞いて、ぜひ訪れてみたいと思っていたのだ。
中仙道の宿場町のこと、木曽義仲の故郷、島崎藤村の生誕地、歴史と文化に溢れる土地に憧れを抱いていた。
三大美林の一つに数えられる私の故郷、秋田の杉林も自慢であるが、木曽の檜林も見事なものであった。八幡平、秋田駒も秀麗だが御岳山、木曽駒の神々しい美しさは言葉にしがたいものに感じ、自然に両手を合わせた。
生保内節も秋田の情緒を調べておるが、「木曽のナァー、なかのりさん」と歌い始める木曽節の調べは、余りにも有名で懐かしいものがあった。
興禅寺の石碑に、山頭火の句「たまたまに まいりし木曽は 花まつり」に触発されて、しばし詩人の気分に浸った。
代官の 清水をのみし 蝉時雨(山村代官屋敷の門前にて)
あきのいろ 恋の調べか 虫の声(陳先生縁りの初恋の小径にて)
また長福寺山門前の掲示板にあった「ぼうふらや 蚊になるまでの 浮きしずみ」を読んで、木曽福島での陳先生の境涯から
讃「天上(てん)の弦 故郷ありて 人とあり 艱難越えた 山のかずかず」”
と無常の境地を讃える。
木曽川の中央橋前にある文化ギャラリーに、陳先生の業績を顕彰する展示物がある。町の歴史と共にあって、町の人々に愛され、尊敬されている在日一世の姿を見ることにより、生まれた短歌なのだ。
四日間にわたる音楽祭での、陳先生が目標とされた楽器作りの究極の逸品ストラディヴァリウスの調べは、陳先生と木曽福島の町を誇らかに祝福しているように思えた。
“小さな町の小さな音楽祭”と銘打たれていたが、どうしてどうして、小さいどころか日本を代表する音楽祭と銘打つべきものではないかと思った。
馬籠宿の藤村の記念館で見つけた藤村の言葉
「血につながる、心につながる、ことばにつながる、ふるさとがある」
は、陳先生と木曽福島の町が、因縁薄からぬものであることを教えてくれるようだった。
私の境涯や、在日の同胞の全てにも繋がる言葉で、ふるさとのありがたさをしみじみと感じた旅であった。
〈木曽福島町名誉町民章受章を祝う言葉〉
二〇〇五年九月の中頃、陳昌鉉先生の奥様、李南伊さんより
「木曽福島町より、名誉町民推戴のお話がありましたが、名誉町民になるとどんな責任と義務があるのでしょう」
とお電話を頂きました。
「責任や義務などはありません。陳先生を愛し、尊敬し、誇りに思っています、という木曽福島町民の純粋なる民意であると思います。世界で五人だけの、アメリカ製作者協会からの〈無鑑査製作家の特別認定とマスターメーカー〉称号に対する業績と、人格を認めて下さったのですから、ありがたくお受けになるのが自然かと思います」
と私は答えました。
私の知るところでは、これまで日本社会において在日一世の韓国人が、特に芸術文化関係では初めての名誉であり快挙であります。
木曽福島町が在日の存在を認められ、知らしめ、陳先生を顕彰して下さることは、在日の我々だけでなく、祖国韓国の人々にも光栄なことであり、誇り高く励みになるありがたいものであります。これは木曽福島町の皆様にとっても等しく大きな喜びで、新生木曽町の門出を飾る歴史的な慶事であるはずです。
お隣の山梨県北杜市高根町五町田出身の方で、戦前に韓国に渡り韓国の土になった人がいます。植民地政策化の朝鮮で、民芸の中に朝鮮民族文化の美を見つけ出し、朝鮮の人々から愛された浅川伯教、巧兄弟です。
弟の巧さんは、林業技手として朝鮮の緑化に尽くし、お兄さんの伯教さんと共に朝鮮民族の誇りである、失われた白磁や青磁、工芸を研究し著書を残されました。朝鮮語を学び朝鮮文化を理解し、伝統文化である韓国民芸に捧げた生涯を送られた方です。朝鮮人は日本人を理解しなくても、浅川兄弟を愛し、韓国人の尊敬を受け、評価を高めております。
今、巧さんはソウル郊外の忘憂里の墓地に眠っておりますが、そのお墓は韓国の人々によって敬愛の情を持って守り続けられております。墓の碑文に“韓国が好きで韓国を愛し、韓国の山と民芸に捧げた日本人、ここに韓国の土になれり”と記されております。
私は在日二世でありますが、在日で生きるための哲学を学んだのが、浅川巧の生き方からでした。正常でなかった時代に、稀有なる人類愛に生きた、私が憧れ尊敬する日本人です。浅川巧は韓国の山河を愛し、歴史と文化を大きく深いところで理解し、国や民族を乗り越えた共生を考えていた、国際理解の視野を持った、国際親善の先駆者であったからです。私はこの度の慶事が、浅川兄弟の活躍と重り思えて、時空を超えた感慨深い熱いものがあります。
温故知新「故きを温ねて新しきを知る」の例えにもあるように、先駆者の教えが木曽福島の人々の心に生きているようで、心が温まります。
陳先生の名誉町民の受章は、共生のモデルとして模範的で誇り得るものであります。普遍的な人間の価値にこそ、人生の指標があるということを、確認させて下さいました木曽福島町の英知と見識に、敬意を表します。陳先生の『東洋のストラディバリウス』が生まれたルーツが、木曽福島の町にあったこと、陳先生の青春を育んだ自然の偉大さ、そこで営まれた人生の波瀾と至高を追及する気高い精神は天と地、そして人知る厳粛なるものであります。
第二の故郷木曽福島の町で、李南伊さんと契りを結ばれ内助を得たことが、陳先生にとっての幸運の原点であったのだと、私は心から祝福致します。
〈木曽を賛辞する〉
「血につながる、人につながる、ことばにつながるふるさとがある」
という島崎藤村の言葉が、陳先生の感懐そのものであると私は喜びを共にしております。
「この世の中に無駄なものはない。あるものは全て必要なものばかり。試練も困難も無駄ではない」
と言う、陳先生が到達した頂きには悟りがあります。
「天(てん)の弦 ふるさとありて 人とあり 艱難越えた 山のかずかず」
後に続く私達は、陳先生の偉業に対し喜びを共にし、希望をもって、この慶事を讃え歌います。
陳先生の『東洋のストラディバリウス』の音色が、日本と韓国を架け橋して、平安と永遠なる友情と親善を奏で、陳先生の名声と新生木曽町の無窮なる発展を世界に鳴り響きますよう、祈りたいと思います。(二〇〇五年一〇月二三日木曽福島町閉町式・木曽福島会館大ホールにて祝辞)
「天国と地獄とその中間の絵画」
画家・呉日(オ・イル)(一九三九~ )
〈接点〉
光州市立美術館主催による、五・一八光州民衆抗争(光州事件)二五周年記念河正雄コレクション『在日作家 呉日展』が二〇〇五年五月開催された。まず、呉日の作品五六点がコレクションされた経緯と、私との接点(縁)を語らねばならない。呉日は広島で、私は大阪で一九三九年に、この日本で生を受けたことから始まる。それからの人生においても、いくつかの共通点を見出すことが出来る。
幼少の頃、一時期それぞれ、韓国の故郷に帰って生活していること。一九六〇年代になって、それぞれ在日本朝鮮文化芸術家同盟(略称・文芸同)美術部会員となり、日本アンデパンダン展に共に出品したことがあること。私が尊敬する宋英玉(一九一七~一九九九)は呉日の先輩でもあり、友人でもあったこと。一九九五年第一回光州ビエンナーレが開催されたが、光州市立美術館河正雄記念室では『光州の五月精神展』が開かれた。その時、私の記念室で宋英玉と呉日の作品が展示され、後日その作品は河正雄コレクションとして収蔵したことなど。
〈出会い〉
しかし決定的な接点は、呉日の支援者であり、在日画家のコレクターであった呉永石先生との出会いである。
呉永石先生の経歴を紹介する。一九三六年東京生まれの大阪育ち。上京し一九六五年、日本デザイナー学院創立。一九六六年日本写真専門学院創立、一九六九年日本ビジネススクール創立、一九七七年学校法人呉学院創立。一九八六年米国セントラルメソジスト大学名誉博士号授受、一九九六年東京都〈学校教育功労者〉表彰を受けている。徒手空拳で学園を創立し、三〇年に渡り週二回の人工透析と聴力の喪失というハンデを負いながら、一にも情熱、二にも情熱、チャレンジ精神の経営哲学で学園を築き、発展させた教育事業家である。在日の文化芸術人達の支援、育成にも尽力され、長年美術館の創設を夢見たが未完成として二〇〇一年に旅立たれた。
一九八四年一〇月、上野の森美術館に於いて〈郭桂晶創作工芸展〉が開かれた。その展示場に呉永石先生が見えられた。その時、
「私は青年期、画家になる事を夢見たが叶わず、二五才の時から主に在日作家達の美術作品のコレクションを開始した。それらの作品で、私が育った秋田県田沢湖畔に、二〇世紀の不幸のために亡くなられた、我が同胞の御霊を慰霊する美術館を建立する計画を立てた。だが、それらのコレクションは、縁あって私の父母の故郷である韓国光州市に全て寄贈する事となった」
とその経緯を呉先生に語った。
「河さん、私の故郷も光州に近い順天です。まだ一度も帰った事がないが、河さんの話を聞いていると、故郷の事が懐かしく思い出されます。私も河さんと同じ気持ちで、在日の作家達の作品をコレクションして、美術館を建てる夢を抱いているのです」
と話された時、私は同じ時代に同じ夢を抱いて生き、同郷である出自を知り、また感性と感覚が私と同質の物である事を喜び、親しみを感じた。
「呉先生、私が故郷の光州に御案内しますから、いつか一緒に行きましょう」
と私は誘った。しかし先生は
「週二回の透析の為、人に迷惑をかける事だし、万が一もある。それは叶わぬ事だ」と話された。
「今は韓国の医学も進歩して心配ありませんから、私に任せて下さい」と重ねて言うと
「私は組織に関わってきた人間だから、今は南の韓国に行く事は出来ないのだ」
と毅然と、しかし淋しげに答えられた。その時、呉先生の望郷の念を思うと切なかった。
私は二〇〇〇年第三回光州ビエンナーレを記念して、光州市立美術館で『在日の人権展』を開催した。この企画を進めるにあたって、呉先生のコレクションの中から呉日画伯の作品を二、三点借りたいと申し入れた事がある。その時、快く承諾いただいたのだが、多くのコレクションの中から捜し出す事は困難である旨を話され、作品を借りる事を断念した経緯があった。
翌年、呉永石先生が享年六五歳で急逝された。早逝の報せは衝撃であり、無念であった。二〇〇四年三月、呉永石先生の妹である呉永順氏より便りがあった。
「学校法人呉学園理事長・故呉永石のコレクションとして残された呉日の作品を、河正雄コレクションとして寄贈したい」
との内容であった。そして六月になって、伊豆の別荘に保管されていたという五一点の作品が、私のもとに届いた。寄贈を受けた呉日の作品は、美術館の夢を果たせなかった心残りを、河正雄コレクションとして光州市立美術館に託されたものではないかと思う。
「いつの日にか、呉日先生の作品展を開催する機会を作りたい。そして呉永石先生の、故郷への里帰り〈望郷〉の思いを叶えたい」
と感謝の言葉を私は述べた。その時、呉永順氏は伊豆高原の別荘を呉永石記念館として開館すると話され、晩秋になってその案内が届いた。
〈呉日は何故画家になったか〉
一九九六年、呉日が我が家を訪問された。その時、呉日は何故画家になったのかと述懐した。
学校と言えば、小学校にしか行ったことがなかった。釜山草梁国民学校に呉日布の名で通い、六年生で中退。一二歳の頃から、家庭の事情で炭坑や染物屋、パチンコ店、皿洗いなど、放浪しながら生きるために下積みで働いた。余りの厳しさと辛い思いだったので、同じ苦労するなら絵描きになろうと決心して、通信で漫画を学んだ。
一九歳の時、画家になるために上京してからは大変だったが、三八年の歳月が流れた。画家になると言う夢は実現したものの、それは決して楽な道ではなく、険しい道のりであった。生きることは闘いであり、人間とは何のために生きているのか?という悩みは、人間は生活するために生きているのだという意味に到達するまでに、長い歳月を必要とした。人間の幸せとは何か、青い鳥はどこにいるのかと探し求めた一つの到達点である。
「私にとっての生の証明をし、これからも、一生絵を描き続け、全う出来れば本望である。絵を描くのは苦しみがつきものだが、また喜びも、生き甲斐も感じる。芸術は表現の世界だが、終わりがない。無限だ。ここのところ、芸術は不毛の時代という。だが人間が存在してある限り、永遠に続くであろう。人間は誰でもと思う事だろうが、私も、神と自然に生かし、生かされていると思う。若い時は祖国の平和統一のために頑張ってきたが、今は一人の画家として生きたい。地球が人間の故郷という時代になったが、今だ解らないことが山ほどある。芸術は未完で始まり、未完で終わるのであろう。しかし創造は戦いだが、苦悩から喜びを味わう幸福だ。人間は自然から生まれ、自然に帰る。表現できる才能を与えられ、神と自然に感謝を捧げる」
と呉日は語った。
芸術に生きることは贅沢なことだ。生きて感動を与えることが、芸術家の目的である。その熱情が恨(ハン)を凌駕したのだと思う。
〈在日の痛ましい断面〉
彼が生きた南北分断による在日の、生の痛ましい断面を語るには辛い。呉日は朝鮮新報社で乗用車の運転手を七年務めながら、朝鮮商工新聞に政治漫画を一年間描いていたが、対話のない生活には耐えられなかった。
一九六五年頃から激化しだした中ソ論争は、必然的に組織の内部に深刻な事態を及ぼし、権力闘争となって分裂・粛正の嵐は、容赦なく反対派を弾圧した。その中には、分派とは無関係なものも数多く含まれていたが、呉日もその一人であった。
生来の性格が災いした。何でも喋ってしまう男であると、危険分子扱いされた。祖国の平和統一のため、革命に生きるか、芸術に生きるか、迷いながら、ひたすら絵を描くことに情熱を注いできた彼は、ある日突然、民族虚無主義のレッテルを貼られて査問に掛けられ、数人の同志から無理矢理大量の薬を飲まされた。そして精神病院の独房に監禁され、自殺未遂を五、六回も繰り返し絶望的な日々が明け暮れたが、死にきることが出来なかった。それ以来、彼は結婚も出来ずに精神病院を往復して、今も安定剤を飲んで、昨日の忌まわしい記憶を忘れようと生きて、この世の地獄と天国とその中間の絵を描いているのだと語った。
イデオロギーが著しく人権を犯し、痛め傷つけた不幸な歴史、私の道程にも少なからず同じ境涯があったので胸が疼いた。呉日の絵は民族史、在日同胞史を語る絵であるといえる。
〈人生は闇〉
人生は闇なのだ。だから希望という光がなければ耐えられないし、生きられない。画家も常に十字架を背負い、一生死闘を繰り広げる求道者である。生の審判が下されるまで、逆境の中で人生の孤独と愛の歌を訴えるのは、人生がテーマであるからだ。
人生は旅である。生まれてから死ぬまでの旅である。一人暮らしで流されながら生きてきた呉日が、人生は〈無〉と解ったという。「有から無は生まれるが、無から有は生まれない」真実は虚しい。だが、その虚しい〈無〉の壁を超越せんと人生に臨むのは、創造の喜びがあったからだ。生と死の悲しみや苦しみを背負い、光を求めてトボトボと浮遊し、光明を求めて漂泊する旅人。生と死を深く見つめるための修行者となって、出家したのだとも言える。それが人生というのでは、余りにも淋しすぎる。呉日は、自身の苦労は大したものではないと思っていると私に語ったが、在日の大方の人生は、悲しいことに似た話が多くありすぎるのは痛ましい限りだ。
呉日の絵は素朴、簡潔、直裁で明るく楽観的に見える。しかし、その裏には淋しさを紛らわせるため、生きる喜びのため、楽しむために描かれているように思われる。望郷の抒情と故郷への夢の中のペーソスとナイーブさという郷愁が滲み出ている。また何故か、孤独で淋しさの中の恐怖への想いと、ブラックユーモアの中にシリアスな抗議と憤怒が漂う。内在する恨(ハン)が、表出して画面から飛び出して来るように訴えるものがある。我々が共感するのは、闇の中で生きた在日の魂が疼くからだ。
呉日は、思想を表現して思想に生きる芸術家を目指したが、思想だけが唯一の生きる道でないことも、真実である現実に戻ったのだ。宇宙原理に運命を委ねる真実とは何か。呉日が求める永遠のテーマでもある。
〈呉日の略歴〉
呉日は、一九三九年一二月二五日に広島で生まれた。
一九六一年から六八年に日本アンデパンダン展出品。私の手元には『一九六一年故郷の母、六二年煙突のある風景、六七年犠牲者・燃え上がる四月、六五年農夫・牛、六六年鳥と少年』の出品記録がある。
一九六二年から二〇〇四年まで、自由美術展に四四回出品。そして佳作賞を二回受賞。現在、自由美術協会会員である。一九六四年から六六年在日朝鮮青年展、一九六四年から六八年平和美術展、一九八三年から八六年黄土展に出品し、個展も二〇〇四年まで三五回を開催している。
一九四五年、呉日は祖母に連れられて韓国に一時帰国して六年間、故郷の慶尚南道居昌にいた。祖国で解放の喜びを味わったのだが、その五年後には朝鮮戦争が始まり、分断の祖国の惨状を見ることとなった。呉日の絵画のルーツは、この頃から全てが始まっていると思える。幼少期に体に染み込んだ故郷の印象、呉日の哲学と人生観は、この祖国で目にしたものが全てであり、その望郷の記憶が年老いても鮮烈なのであろう。
故郷を後にした一二才の時、対馬から鹿児島へ、そして大阪、転々として東京へと辿り着いたのである。在日と祖国との狭間の中にあった歴史の不幸が、呉日の絵画様式であり表現であるとも言える。
〈呉日へのエール〉
「呉日さんの絵画は、こざかしい技巧の積み重ねで、人の気を引く世界ではない。それは真っ直ぐ凝視する眼差しによって、喜びも哀しみも、絶望も希望も、呉日さんの心の湖に波立ちながら映っている。それは在日コレアとしての避けがたい波立ちの、いわば恨(ハン)を起点としている。在日に対する、または在日同志の差別、少年の時に帰郷したときの強烈な体験、そして中ソ論争を契機に起こった在日同胞同士の悲しむべき悲劇、それらの苦しい道筋の中に、呉日さんの抑えきれない感情が描き出した線があり、記憶や郷愁が絞り出した赤い色彩があり、怒りに膨らんだ表情がある。
呉日さんの世界は、今世界中で苦しみながら、それでも生き抜こうとしている人間達の心と結び合い、共有されていくのだ。私には呉日さんが闇夜に消されまいと火をかかげて、神を探している人のように見える。どんなに苦しくとも絶望したり、虚無主義者になったりしないで、絵画という手段を通して、人間の生命の有り様を凝視し、希望への道を求め続けている画家だと信じている」
「呉日さん頑張れ、こんな時代に負けるな」
とヨシダヨシエ(美術評論家)は応援する。
骨や髄、歯茎までに染み込んでいる恨(ハン)の感情。歴史的な不運や災難。運命に振り回され思い通りにならない、力が及ばず、常に戦争と過去に囚われる感情・恨(ハン)。それは私にもある感情であり、日本人にもある感情であると思われるのは、時代の共有感からであろう。
私と呉日は境涯こそ違えども、在日を共有して生きたことの事実は、何ものにも代え難い共感の価値である。来世に希望と光を、そして夢のある人生を願い、祈り呉日は歩む。私も共に今歩んでいる。
「祈りの芸術」
画家・全和凰(チョンハァハン)(一九〇九~一九九六)
〈はじめに〉
過ぎ去った時代の屈折の中で、数多の在日韓国人は、日本の空を流浪する亡国の旅人となった。万の辛苦と苦痛に耐え忍び、戦後の貧困と偏見の中でも、粉骨砕身ただ一筋の光を希求しながら、祖国の宿命と共に耐え抜いてきた。
それは、〈雑草の中の花〉のような永い永い苦悩と試練を超え、平和の念願と望郷の夢で凝縮された在日韓国人の実像を、まさに全和凰の芸術がすべてを表している。
いわゆる在日韓国人二世として、真正の魂のルーツを失っていた私は、彼の作品に初めて出会った時、激しい感動と戦慄におそわれた。それ以来、その『祈りの芸術』を誇らしく、光の注ぐ場所に出して、広く世の中に紹介し、守り、育成していかなくてはならないという、義務感と使命感のようなものを感じて生きてきた。
私は、父母の故郷である光州市立美術館の積極的な要請に応え、収集した大部分の在日同胞の作品を寄贈、九三年そして九六年に『祈りと求道の芸術-全和凰回顧展』を開いた。
そして九七年には、第二回光州ビエンナーレ記念展で、全和凰の真髄をより広く国際美術界に紹介することができ、真に胸熱く歓喜をおさえることができなかった。数百万の在外韓国人の貴重な記録であり、歴史であり、文化遺産である全和凰の芸術世界が、深い共感と共鳴をわかちあったからだ。
全さんは、ホトケさんを描く重鎮画家として、日韓画壇で広く知られている。
全さんの描いた『弥勒菩薩』や『百済観音』『阿修羅像』は生きているようである。
また全さんは「花の美しさよりも花の精を描きたい」と〈牡丹〉や〈雑草の中の花〉なども好んで描いた。それは人間の煩悩を知りつくした、求道心と信仰心の強い、静かでおおらかな姿である。全さんは、苦しみと悩みからの解脱を仏陀に求めたようにも思えるが、現象や物事をしのぐより、深い精神性の高い対象と自己を静かに対立させる芸術理念の具顕は説得力を持っていた。〈祈りの芸術〉と評され、〈宗教的な詩情〉を漂わせた現代美術に欠如している風土性の濃い表現だ。
「高麗青磁の淡くあたたかな白濁の美しさがある」と寺田透は評し、
「この画家の画の上質のものには、朝鮮の古い伝統につながる静けさや淋しさが、そこはかとなく感じる」と谷川徹三は評した。
〈全和凰の略歴〉
全さんの真摯な生きざまには、不幸であった祖国と日本との狭間の中での苦悩にみちた、沈痛なる生の闘いが綴られている。
一九〇九年平安南道安州に生まれ、本名を鳳済という。二〇歳で朝鮮美術展に入選し、東亜日報、朝鮮日報に童話童画を発表した。
「そのころ、日本の憲兵や警察の圧力はたいへんなもので、まともな人間生活はできないような状態で、我々朝鮮人はいかに生きるべきか、この問題を解決しないでは絵を描けないと悩みました」
二六歳の時、西田天香の『懺悔の生活』を読んで出家、托鉢行脚の修行の途につき一九三九年、京都の一燈園に入園した。
「当時の青年たち誰もが体験した植民地政策のせいであったが、私は絵筆を捨てて一燈園に飛びこんだのです」
そこで運命的な師・須田国太郎との出会いが、日本での画家としての出発点となる。須田国太郎から作風に大きな影響を受け、また京都で幸運な仏像たちとの出会いともなるのである。
一九四七年『一燈園風景』で京展賞、一九五一年『群像』で行動美術賞受賞、五三年には行動美術会員となる。この時代の代表的な作品には『カンナニの埋葬』『避難民』『アリラン峠』『再会』などがあるが、モチーフは祖国の惨状であり、社会的なテーマを描いた抗議の作品である。五〇年に描かれた『ある日の夢・銃殺』(京都市立美術館蔵)は三・一独立運動の一場面であるが、祖国や現実の社会の矛盾に向けた代表作である。これらの作品の特色は、観念主義でも政治主義でもない。精神的な詩情を漂わせた、本質的に自由人の魂を強く印象させる表現主義である。
一九九六年一〇月三〇日から一四日まで、光州市立美術館で全和凰展が開かれた。
一九五〇年代から八〇年代までの代表作九二点の展示である。これは九三年、私が光州市立美術館に寄贈した在日同胞作家全和凰、郭仁植、宋英玉、李禹煥、文承根、郭徳俊計六名二一二点のうちの、全和凰の全作品である。
「この機会にぜひ、期間中に光州市立美術館を訪問して下さい」
と案内を差し上げたのが九月中旬のことであった。
一〇月八日午後一〇時過ぎ、
「全ですが」
と電話がかかった。私は、全さんが光州に出掛けてくださる返事かと思って受話器を取った。全さんの奥さまからの声であった。
「一〇月七日、全が亡くなりました」
との知らせ。私は動転してしまった。二年前、『レスチンで一二〇歳も可能』(燈影舎刊)という本を出版された時
「私は一二〇歳まで生きる」
と元気に話されたことが夢幻のようであった。
〈純粋な人類愛〉
二〇数年前のこと。新宿のデパートに向井潤吉の『民家』の絵が掛かっていた。ファンであった私はその絵を求めようとした時、その並びに全和凰の『弥勒菩薩』が掛かっていた。その出会いは運命であり、因縁であった。私はその『弥勒菩薩』との出会いが縁で、全さんの作品をコレクションすることとなったのである。
八二年、全和凰画業五〇年展を企画し、東京、京都、ソウル、大邱、光州と巡回展を開き、そのとき『全和凰画集』(求竜堂刊)をも発行し、私は全さんの美の心酔者となったのである。
人生を共に生き歩んだと言ってもはばからない。全さんの心の遍歴が共感となり、わが父母の苦難、在日が、祖国が共鳴したからだ。
「私は、世界は一つだと思っています。北とか南とかいうのはまちがえていますよ。私自身は政治に関係ない。ただ雑草のごとく、根強く生きながら、やっぱり平和を望む生き方をしたいんです」
全さんのヒューマニズムは、純粋な人類愛、世界平和への高邁な理想として残したことを祝福して送りたい。ご冥福をお祈りする。
「湖畔のほとりから」
画家・郭仁植(カワギィンシック)(一九一九~一九八八)
〈出会いと別れ〉
朝日新聞の文化欄に『郭仁植展』と『全和凰画業五〇年展』の美術評が同時に載った。一九八二年一月一六日のことである。その時私は、銀座のセントラルアネックスで『全和凰画業五〇年東京展』を開いていた。以前から郭先生のことは知ってはいたが、一度もお目にかかったこともなく、作品に接する機会もなかった。
知っていることは、どちらも在日の一世であること、元老的画家で片や具象、郭先生は抽象現代絵画という程度の知識であった。
その時、時も同じく銀座で『郭仁植展』が開かれていることを知り、偶然ではあるが縁を感じない訳にはいかなかった。お目にかかろうと思い、「ギャラリー手」に伺った。あいにく先生は不在であった。そこで初めて先生の作品に接したが、私はそれまで抽象絵画には興味も好奇心もなく振り向きもしなかった。不器用なほどに一人全和凰の世界で遊んでいたのである。
朝日新聞の米倉守さんは郭先生の作品を『静寂の美』、全先生の作品を『鎮痛の美』と書かれた。私は二人の世界も表現もまるで違うが、共に『祈りの美』ではなかろうか、そう書かれていると理解し、こだわり続けた。五月の京都展を終えて、ソウル展開催のため二週間程ソウルのプラザホテルに私は宿泊していた。その時、友人の画家郭桂晶女史が知らせてくれた。現代画廊での個展のため、数日前から同じホテルに郭仁植先生が泊っていると。私は不思議な縁を強く感じ、初めてお目にかかった。なんだか前から何度もお会いしているような気持ちであった。先生は私のことを良く知っていたらしく、親しみを込めて接してくれた。
「美術をやるものとしては、君のように絵の好きな人が好きだ」と好意を示された。
全先生とは若い時から尊敬しあい、初期には同じ具象の道を歩んで共に苦労した仲であると、私と全先生の出会いをことのほか喜んでくれた。
私はその時、次の大邱展の準備に入っていた。その事を話したら郭先生は
「私の故郷は大邱で、初めて錦を飾る個展を近い内にやることになっている。私の夢は、故郷の大邱に美術館を建てることだ」
と目を潤ませながら語った。その時、どこか体が悪そうに感じた。とても疲れていると言っていたし、顔もやつれ切っていた。しかし意気は燃えていた。
「私はこれからなんだ。国立現代美術館での個展も決まり、これからなんだ。見ててくれ」
と何度も何度も繰り返した。私は祝福しながら身を案じ、大邱で郭先生の夢が叶うよう祈りつづけた。
よく夏、新宿の高野のパーラで再会した。とてもしゃれたアロハシャツ姿で、サンダルもモダンで、芸術家の香りがあふれ輝いていた。
「これからは、ニューヨークにも進出するよ」
とソウルでの弱々しさが嘘のように、明るく華やいで元気を取り戻されていたことを喜んだ。
「君に見せたい昔の絵を、火事で燃やしてしまい、残念だ」
と悔しそうに、涙を浮かべていた瞳が忘れられない。この会話が最後の別れとなった。
私の幼い時からのロマンは、故郷の秋田の田沢湖畔に『祈りの美術館』を建てること、これが私のライフワークであった。伊丹潤(庚東竜・建築設計家)先生を田沢湖にご招待したことがある。私は関係する湖畔のサンライズホテルのフロントに、湖のきらめきのような郭先生の作品を掲げていた。伊丹先生はめざとく、その作品を見られて
「私の最も尊敬する郭先生の絵が田沢湖にあった」
と顔をくしゃくしゃにされ、私と郭先生との出会いを我がことのように喜ばれた。郭先生は、田沢湖での私のロマンが咲くよう暖かく見守り続けることであろう。
駐日韓国大使館の大使館邸賓客のための広間に、郭先生の二百号の作品が掲っている。慈愛を受けている韓国現代美術館長も務められた尹鐸公使の依頼で貸し出したものであった。韓日の賢人会議や国際的な賓客をもてなす広間の壁が淋しいと話されたからだ。私は躊躇せず、郭先生の作品を掲げることに意義を持ち誇りとした。その作品には〈祈り〉の響きがあり、燦然と矜持を保ち続けている名作である。
先生の訃報を知ったのは光州であった。先に述べた全和凰大邱展のあとに光州展を開いたが、その時、光州の盲障害者との縁が出来た。光州市に、光州盲人福祉会館を建立するためこの数年足しげく通い続け、やっと一九八七年一一月着工され、一九八八年四月開館のメドを立てて日本に返ってきたところに、この追悼文の原稿依頼があった。私は郭先生との出会いの中で
「先生の作品は色盲の検査の図柄のようだ」
とトンマなことを言って笑い合った。その時のなんともいえぬ細い、優しい目の笑顔が焼きついて忘れることが出来ない。
〈郭仁植の美術世界〉
郭仁植は一九一九年韓国慶尚北道達城郡玄風面上洞に生まれる。一九三七年(一八才の時)、父親の勧めで早稲田大学商学部に留学する為に来日したが、現武蔵野美術大学の帝国美術学校に入学してしまった。二年後、帝国美術大学の内紛のため、現多摩美術大学の多摩帝国美術学校で学ぶ。
一九四〇年、故郷である大邱の三中井画廊で初の個展を開いた。一九四九年には二科会に参加するが、「祖国平和統一・南北文化交流促進文化祭」「南北合同文化祭」などを通じて、祖国の平和統一を願いながら活動を続けていた。
一九六一年八月一五日、祖国解放一六周年記念第二回連立展には「黒の空間」と「赤い大地」の油彩二点を出品した記録がある。これらの作品は焼失してしまったと、郭仁植は悔しそうに語った。重厚なマチュエルで、写実を超えたシリアスな表現の作品であったという。
六〇年代に入りガラスを使った作品、そして金属板を切って、繋ぎ合わせたり、その表面に穴を開けたり、溝を付けたりした前衛的な作品を発表。物質表面に関わりながら表現した作品は、日本の美術界に衝撃を与え『モノ派』の先駆者といわれるようになる。
「郭仁植のガラス作品には、『具体』と『モノ派』の美術史との関係を繋げるよりも論理的であり、『モノ派』的だったと言える」
とギャラリーQのオーナー上田雄三氏は評している。
一九六八年、東京国立近代美術館での韓国現代絵画展、一九六九年、サンパウロ・ビエンナーレでは木・鉄・紙の作品を発表し、この頃より和紙に彩墨の作品を発表するようになる。七〇年代に入り日本、韓国、シドニー、ロサンゼルスなど、個展や招待展で発表し、世界を舞台とするようになっていく。
一九八四年、私は郭先生のお誘いで稲城市の画室を訪ねた事がある。絵の具や毛筆などが整然と並べられ、静謐感漂うアトリエであった。壁面には、禅の修行で描いたと思われるような点描の作品が架かっていた。その作品には凛とした気品と祈りを感じて、私はコレクションする事にした。和紙やキャンバスを物質的な表面として扱っている作品の一点で、後に韓国大使館に貸し出したものである。
一九八五年には、ソウル徳寿宮の国立現代美術館に於いて、在日作家としては初めての回顧展を開いた。その先駆的で刺激的な作品、透明なる色彩感覚は韓国美術界に新鮮な息吹を与え、その芸術性は日本と韓国で高く評価されている。
〈回顧展開く〉
私は二〇〇二年六月、第四回二〇〇二光州ビエンナーレを記念して郭仁植回顧展「韓日現代美術五〇年の礎・郭仁植の世界-河正雄コレクションを中心に」を開催した。
一九九三年、光州市立美術館に寄贈した郭仁植の作品と、二〇〇三年新たに郭仁植のドローイングと版画三〇〇余点、そして遺品や写真など二〇余点を追加寄贈した両方を併せた作品の特別展である。初期の油彩作品からガラス・真鍮・石・紙などの物質を使った作品、そして後半期の和紙に墨彩による点描作品まで、郭仁植の画業が辿れる展示となった。
三〇〇余点のドローイングと版画は、晩年の郭仁植の内弟子のような立場にあった上田雄三氏が、奥様より遺品として譲り受けたものを、河正雄コレクションに寄贈された作品である。
その作品は、風景スケッチやヌードクロッキー、ミロやアンドレ・マッソを思わせるシュールレアリスティックなエスキースやデッサンなどである。その素描群は、物質と表面の関係に拘り続けた郭仁植とは異なるモード性の高いデッサン群で、キュビズムやシュールレアリズム、アンフォルメルの影響を強く受け、内部に取り込んだそれらを、創作欲の赴くままに描き出した郭仁植の混沌とエネルギーの塊のように私は感じた。この素描群は六〇年代を境に、郭仁植が芸術家としての転換期を迎える重要な意味を持つ貴重なものである。
郭仁植は韓国、日本のみならず東洋、そして世界の現代美術史にとっても欠かす事の出来ない重要な作家の一人である。
「願望 告発 安らぎ」
画家・宋英玉(ソンオック)(一九一七~一九九九)
四月九日深夜午前二時、電話が鳴った。先月、ある会合でお目にかかった呉日画伯からだった。
「宋英玉先生が亡くなられました!」
在日一世の宋画伯の突然の訃報に、満開の桜が一夜にして散った思いだった。
〈出会い〉
振り返ってみれば、画伯との出会いは、一九八一年正月のことだった。
銀座のセントラル美術館で開催された『全和凰画業五〇年展』の会場にお見えになったのである。背筋が物静かなベレー帽姿は、芸術家の香りが漂い、頼もしく感じた。
「一度遊びに来ませんか」
と誘われて訪ねたアトリエは、寝食を同じくする薄暗い木造のアパートの一室であった。その一隅で、画伯はキャンパスに向かっていた。その脇には、何度も塗りこめられた夫人の肖像画が飾られていた。最愛の奥さんを最近亡くされたとのことで、今もその淋しさから立ち直れずにいる。室内は雑然としていたが、何も手をつける気になれないのだと、画伯はすまなそうに語った。
画伯は家族に看取られて静かに眠られていた。鼻筋が整ってキリリとした厳粛極まるお顔からは、八二年の労苦が嘘のように消えていた。画伯は何も語ってくれなかったが、ようやく最愛の奥様のもとで安らいでおられるのだと思った。
〈在日としての画伯〉
画伯の在日としての現世は、辛くて苦しくて、赤貧洗うがごとしの人生であった。しかし、画伯には生きて生き抜いた、確固たる芸術家としての誇り高い足跡がある。画伯の遺した作品群は、永遠なる輝きを放つ生命力をもっている。言い換えれば、画伯は永遠に生き返り、二〇世紀を生きた在日の時代と世界をメッセージに託した作品を遺したのだ。
原爆の惨禍に平和への祈りを込め、原爆ドームが浮かぶ川面に流れる灯籠を描いた『灯籠流し』。広島で、太平洋戦争で犠牲になった多くの同胞に対する哀悼と慰霊を、そして物静かに戦争の愚かさと空しさを訴えている『五・一七』という作品では、祖国光州の民主化抗争を、国民に向ける兵士の銃口のもつ意味は何なのかと問うている。民主の尊さを守るとは、いつも銃口にさらされているものだと警告しているのだ。
また、九〇年の自由美術展で平和賞を受賞した『百済観音像』には、長かった苦闘の自らの救済をも具現され、安らかな祈りの世界が描かれている。痛ましかった二〇世紀を浄化し、苦しみの根源を『百済観音像』に救済を求める画伯のたどり着いた、澄んだ境地である。
〈時代の流れと変化〉
一九九八年一二月から四ヵ月にわたって、ソウル国立現代美術館別館徳寿宮美術館の開館記念展が開かれたが、テーマは『再び捜し出した近代美術』であった。同展は、日本による植民地支配や朝鮮戦争(六・二五動乱)によって、所在がわからなくなっていた作品や、個人収蔵のため公開されなかった作品にスポットを当て、韓国の現代美術を再評価しようというものである。
一四六点の出品のうち、在外同胞の作品として一四点の油絵が展示され、〈在日〉からは全和凰、曺良奎、そして宋英玉の油絵が各二点ずつ、計六点展示された。韓国美術絵画史の中で、これまでブラックホールのような存在だった在日作家の作品はそこで見直され、注目を受けたのだから、時代の流れと変化を実感する。
わけても、一九六〇年に描いた宋画伯の『女手品師』は大きな関心を呼んだ。手品師がハンカチの中から平和(鳩)を取り出し、平和の子供(卵)を指の中から生み出していく場面を描いている。同族相争う祖国の現状を、芸術の巧みさで見事に描き出し、そこに平和を祈る作者の心情を注ぎ込んだ。観覧者に大きなインパクトを与え、作家の存在感を示し得た傑作である。
一九九三年、縁あって在日作家六人の描いた作品二一二点が、光州市立博物館の永久展示室に展示されることになったが、宋画伯の作品は一八点収蔵、常設された。今春、再び宋画伯の作品三〇点が、同展示室に追加収蔵される。その作品群は『犬』のシリーズで一つの頂点を迎えるが、その『犬』の姿が自画像に重なり、歴史の暗部を黙示し、時代を告発する作品で、彷徨の自画像ともいえる。これらのシリーズには、反抗と生命の躍動感が溢れ、作家の悲しみや苦しみが共感される。
画伯は現世を去られ、悲しみに堪えないが、光州市立美術館で画伯の作品は、新しい生命として復活するに違いない。
謹んで哀悼の意を表し、ご冥福を祈りたい。
「追憶・一筋の光を残して」
画家・文承根(ムンスングン)(一九四七~一九八二)
〈はじめに〉
私は一九八二年春、全和凰画業五〇年展をソウル文芸振興院美術館で開いた。解放後、在日同胞を初めて韓国で紹介した大展覧会で、これが契機となり、祖国の美術界が在日美術家の存在に関心を向け始めたと言っても過言ではない。
そしてその年の秋、徳寿宮の国立現代美術館で在外作家招待展が開かれた。その時、私は在日作家の推薦を依頼され全和凰、郭仁植、李禹煥、郭徳俊を紹介した。そこにもう一人、私の知らない作家、文承根が推薦招待されていた事を知ったのは後の事であった。文承根については、在日の二世、京都在住の作家であるという情報だけであったが、私は新鮮にその名を記憶に留めていた。
〈文承根追悼展〉
一九八四年七月の事である。郭仁植先生から
「ギャラリーQで、文承根追悼展を開いているので見てくれないか」
と電話があった。私は急ぎ、郭先生が待っていらしたギャラリーQに向かった。
「惜しかった。文承根は病気の為に、余りにも早く亡くなってしまった。これからが楽しみだったのに」
と、我が子を亡くしたかのように郭先生は呟かれた。不覚にも、私の記憶に文承根が刻まれた一九八二年に彼が既に逝ってしまった事を、郭先生から電話があるまで知らなかったのである。
「河さん、一点だけでも良いから、文承根の作品を買い上げてもらえないだろうか」
と郭先生は申し訳なさそうにおっしゃった。私は展示されていた作品の中から、一二点をコレクションする事に躊躇なく決めた。
「有り難い。遺族の生活の事があるので頼んだのだ。助かった」
と我がことのように感謝されていた。
〈出会い〉
私は、郭先生と文承根との関係や縁については、何一つ聞かされていない。同じく、ただ美術の道を歩む在日二世、文承根に対する天賦の才を郭先生は確信していたようで、その早すぎる死に無念さが滲んでいた。私は郭先生に、文承根の遺族に会いたいからと消息を尋ねた。
「この追悼展の作品は、奥さんの手元にあった物であるが、遺族の消息は、今はわからない」
と答えられ、この追悼展の為の文集を渡された。文集の中には、李禹煥先生の一文があった。その一文によって、文承根と李禹煥先生との縁故を知る事となった。
その後の一九八六年一一月、李禹煥先生と初めてお会いする機会を得た。その時、私は文承根への一文を思い出し、その事をお聞きした。
「いつも、何か痛みを持ち続けながら製作に挑んでいた。文承根は才能があった。惜しい友人を亡くしたと思っている。同胞として、先輩として何故、生きている時に温かい言葉をかけてあげられなかったのかと、今も自責の念に駆られている」
と言った。文承根との一期一会の出会いを語る肉声は震え潤んでおり、李禹煥先生の文承根への強い想いを感じた。
文承根を偲んで一九八四年九月四日から三〇日、京都の梁画廊で文承根展。そして一九八六年二月四日から一六日、’86射手座企画展 読むオブジェ 文字と物質が京都のギャラリー射手座で行なわれ、文承根と共に建畠哲、河口龍夫等一〇人が出品し、追悼した記録がある。以後、文承根は韓日の画壇から忘れられた存在となった。
私は縁あって一九九三年、開館間もない光州市立美術館に、全和凰、宋英玉、郭仁植、李禹煥、郭徳俊、文承根の六名の在日作家の作品二一二点を寄贈した。ギャラリーQでの追悼展でコレクションした文承根の作品は、こうして祖国の美術館に収蔵され、名を記すこととなった。
〈追悼〉
東京国立近代美術館学芸員(美術評論家)、千葉成夫氏は
「文承根という部屋は、河正雄コレクションの巣の中では、一番小さい、ささやかなものである。それは彼が三四才で夭折したからである。在日二世として生まれた彼は、始め藤野登と名乗り、病と表現とに悩み、苦しみながら、しかしそのことをあまり表に出すことなく、作品の展開も十分に遂げることができずに、癌のために死んでいった。雨の日に濡れて曇った窓ガラスをこすると、戸外の風景の一部が多少ぼやけて見えたりするが、彼の作品の中にそんな感じの版画作品がある。彼の生そのものが、それに似た印象を残しただけで、火を消した。河正雄コレクションの在日作家の六人の中で、唯一の純粋戦後世代作家だったのに」と惜しんでいる。
「文承根との出会いは一度きりであった。文承根のストイックで禁欲的な作品が好きで、今でも絵を掛けているファンの一人である。特に色彩、グラデーションの繰り返しの作品は印象的で、作品から、文承根という人間自身が伝わって来るように思う。自分も作品を作り発表してきたが、決して真似できないものだった」
と芦屋市立美術博物館学芸課長・河崎晃一氏は文承根を追憶している。
翌年、光州市立美術館より河正雄寄贈作品集の編集を頼まれたが、私の手元にある文承根についての情報や記録は余りにも少なく、唯一収集した顔写真一枚は淋しげで虚ろな表情が、何とも心に引っ掛かり、その時の作家紹介文は、頼りなく中途半端なものであった。在日の幻の作家と言ってもいい存在であったから、文承根の存在は常に気に懸かるものであった。
〈甥文清治との出会い〉
二〇〇一年五月、光州市立美術館は光州民衆抗争二一周年を記念して、河正雄コレクションによる『光州の記憶展』を開催した。在日画家の金石出、日本画家の富山妙子、韓国画家、パク・ブルトンの三人展である。この企画は韓国では初めてのもので、八〇年代に在日、日本、韓国の三人の画家が光州民衆抗争をテーマにした作品を製作し、二〇〇〇年代になって始めて公開するということで大きな話題になった。
そのオープンの日、日本から一枚のFAXが届いた。
「私は京都の文清治と申します。文承根の母親、河福姫が河正雄先生のことを探しております」
という、私が長年探し求めていた内容のものだった。もう文承根との御縁はないだろうと諦め、忘れかけていたところに届いたこの報せに、改めて不思議な御縁を感じながら、京都に出向した。FAXの差出人は文承根の甥であった。子供のいなかった文承根は、死の間際に文清治を養子縁組しようと家庭裁判所に手続きをとり、認可の判決が出たのだが、その手続き中に亡くなってしまった。だから文承根は自分の父のように思っていると、彼は語った。
文承根の母親、河福姫は私と同じ本貫晋州河氏、慶尚北道判順の出身、私の母の一つ下で一九二一年生まれであった。甥の文清治、母親の河福姫の口から明らかにされた文承根の出自、生い立ちと闘病の事を綴ることにする。
〈生い立ちと闘病〉
父、文亀煥は本貫南平文氏、大邱出身、文承根は一九四七年一二月九日、上に兄と姉、下に妹の次男として石川県小松市で誕生した。四~五年小松市に居住した後に京都札の辻に移転。父は織物やいろいろな品物の販売をして、八王子や相模原を転々とした。その頃、母は紡績工場に勤め、文承根は豆腐を売り歩き糧を得ていたという。その境遇が、秋田で少年時代を過ごした私自身とダブり、涙が溢れてきた。生活のために、私も小学生時代に豆腐、コンニャク、トコロテン作りのアルバイトをしていたからだ。文承根が小学校五年生くらいの頃になって、父の事業(貿易業)が成功し、徐々に不動産業、金融業等に手を拡げていった。
文承根は小学校四年の頃から柔道を始めていたが、六年生の頃、練習の最中に体の不調を訴え病院に行ったところ、腎臓の病気が発覚した。その際、柔道をやめるよう言われたという。
文承根の小学校卒業と同時に、一家は大阪に引っ越しをした。文承根は中学校に入学したが、定期的な通院を余儀なくされていた。中学三年の頃、白い小便が出て、大阪の日赤病院に緊急入院し手術を受けた。
文承根は、大阪府立天王寺高校を二年で中退した。その後、学校の近くにあった大阪市立美術館付属美術研究所で約二年間、デッサンなどを学び、美術の道に足を踏み入れていたという。
一九歳の頃、再び京都に引っ越し、京都の日赤に入院。週二~三回の透析は一九七七年頃から受け始め、入退院を繰り返しながら作家活動をしていた。透析の費用は、月額六〇~七〇万円位。区役所に申請すると透析の費用が無料になるという主治医の勧めで、高額医療費の還付を請求するために区役所に行ったが、社会保険をかけていなかったため一部認められなかったようで、病院の費用は父の亀煥が捻出していたという。
一九七五年、文承根は白子(本名・萩野和枝)さんと結婚した。結婚後、まもなく学校に絵を指導に行くようになり、同時に絵画教室も開いていた。文承根が指導していた絵画教室は、スタジオンという名で、自宅の一階部分のアトリエで教えていたようだ。学校は二年制の昼間部を教えていたという。京都芸術短期大学か、レイデザイン研究所もしくはマロニエのいずれかあると思われる。
文承根は、父が経営するサウナ風呂や、飲食店(京料理・割烹)等を体調の良いときに手伝い、画材等の購入をしていた。本格的に絵を始めた頃、そのサウナ風呂で女性をモデルにして八ミリ映画を製作、発表した。リアルタイムで発汗する様の映像は、生身の刺激的なものであったらしい。始めは映像作家を目指していたのかもしれない。
一時、山科にアパートを借りて住んだり、東京の福生に友人達と部屋を借りて住んだりもしていたようだ。その頃、京都の親戚が経営する国際ナイトクラブ〈交差点〉の壁面に、当時のお金で二〇〇万円程を貰い、油絵を描いたり、親しくなった日赤の先生に頼まれ絵も描いたりもしていたようだ。
〈還らぬ人〉
西大路九条に父が三階建ての家を建て、文承根はその一階部分を住居兼アトリエとした。その頃、よく遊びに来ていた絵の仲間達は、具体美術に所属している人たちが多かったようだ。彼らはボロボロの汚いジーンズを履き、ヒッピーのように髪と髭を伸ばし、当時の文承根も同様の格好であったようだ。よく酒を飲んでは、芸術論や絵画論で喧嘩をしており、若さと情熱がたぎる良い時代であったようだ。
体を案じた母親は
「こんな体では長生きは出来ないだろう」
と彼を不憫に思い、そういう事を考えると夜も眠ることが出来ず、胃を悪くしてしまったという。しんどい体に無理をしたらいかんと言ったら、絵を描いているからこそ、しんどさや病気の辛さを忘れる事が出来る。生きる為に描き、教えているのだと言った。床から起き上がることの出来ない体力でありながら、人前では決して弱音や痛みを見せる事も無く、人の気遣いを逆に気遣う。芸術的無知や一般的有識からはひどく外れているように見えていて、美術に対し、実は先頭を切って走っている自負と覚悟があったようだ。
「登は小学校一~二年生の頃から、学校から帰ると一人で黙々と絵を描いていた。頭が良くて、性格が良くて、素直なこんな良い子が早く死ぬなんて」
と運命の理不尽さを嘆きながら、母・福姫は語った。
意欲的な作家活動と闘病生活の中、病状は悪化していった。文承根は亡くなる数ヶ月前から、梅原猛の『仏教の思想』、阿含宗の本など仏教関係の本を多く読んでいたという。迫り来る死を予感していたのかもしれない。最後には、文承根は膝を立てたままの姿で硬直し、その体を父親、文亀煥は摩りながら
「アイゴー、アイゴー」
と必死に息子に呼びかけていたという。程なく救急車に運ばれ翌日、還らぬ人となった。
文承根の死後、白子さんは保母として保育園に勤めていたというが、奥さんは故人への想いを一切断ち切るためなのか、文家には連絡をとらなくなり、消息が途絶えたという。
「奥さんの資料の整理の仕方を見て、本当に深く文さんを愛していたと感じた。二人は似合いのカップルであった。お互いに尊重し合い、大事にしあった夫婦であった。そんな二人に私は好感を抱いており、文承根の作品が好きになった理由の一つにもなっていた」
生前、折々に交流があり、葬儀にも参列した京都国立近代美術館学芸員・河本信治氏は語った。
残された数少ない写真の中に、結婚式の記念写真があった。その写真には、媒酌人として出席していた若き日の郭徳俊御夫妻が写っており、人の繋がりの不思議さを思わせた。
文承根の遺骨は京都にある東福寺・塔頭の万寿寺(東山区)に長い間、納骨されていた。万寿寺の故尹一山和尚様とは、八五年秋田の乳頭温泉郷で偶然、お目にかかったことがある。一期一会ではあったが、ご縁深いお方である。一九九七年になって、甥の文清治が大阪府柏原市の御堂総本山柏原聖地霊園に墓を建て、文承根の父と共に埋葬し祀ったという。父、文亀煥の懐の中で共に安眠していることを確認出来た事で、私は胸を撫で下ろすことが出来た。
〈在日に生きる苦しみ〉
文承根の境涯の中には、色濃く戦後の在日の歴史、ひいては家族哀史が滲んでいる。青年期、日本人藤野登として振る舞い、韓国人文承根として名乗る事が出来ず悩んだという事は、在日として生きる者の踏み絵である。絵を描くことを、生きる全ての手段にしたことで吹っ切り、文承根は自己と民族的アイデンティティを確立し、彼の世界を創造した。在日を生きる辛さ、苦しさ、そして病いをも宿命とした。彼は、どうしようもない苦悩の全てを受け入れ、生のバネにし、人生の闘いに挑んだが、病に勝てず早逝された。
私の場合は、画家になりたいと望んだが、それでは生活が成り立たない、まず生きなければならないという事で、心ならずも画家への道を断念した。在日の歴史の中には、このように時代に阻まれ、境遇に押し潰されたいろいろな形の志と人生の無念さが、色濃く漂っていると言える。私と文承根の生涯も、道は違えども、そのようなものだったと思われる。
文承根は、六〇年代後半の具体展のリーダー吉原治良に認められ、具体の新人展に出品するようになった。文承根の美術界へのデビューは一九六八年。その翌年には第五回国際青年美術家展で、その非凡さを顕わし、李禹煥が大賞、文承根は美術出版賞を受けている。
一九七七年には第一回現代日本版画大賞展でアルシュ・リーブ賞を受賞した。印画紙の上に現像液を染み込ませた刷手ではいた刷手目の中に、日常的な点景である『車の中から見える風景』は、写真製版を効果的に使い、異質の視覚的空間を作っている。その作品は版画界に新風を吹き込んだ。
韓国に進出し、ソウル国立現代美術館でのエコール・ド・ソウル展、韓国現代版画・ドローイング大展、ソウル版画ビエンナーレなど発表の場を広げ、在日を代表する現代作家として世界にデビューする目前に、一筋の光を残して、まるで流れ星のように儚く消えていった。それは余りにも無慈悲な旅立ちであった。
〈遺されたメッセージ〉
文承根が亡くなって二三年となった。この度、二〇〇四年光州ビエンナーレ記念光州市立美術館主催:河正雄コレクション『文承根展』が開催される。会期は二〇〇四年九月一一日から一〇月一〇日までである。
韓日美術史の中で、彼の画業を見直し、問い直し、偲んでみることは意義のあることである。郭仁植、李禹煥、郭徳俊、そして六〇~七〇年代に親交のあった今井祝雄、植松奎二等多くの人々に愛され惜しまれた文承根は、かけがえのない星であった。現在においても、彼の息吹は新鮮に、我々の感性に響くことに気付くはずだ。長い間、幻の中で彷徨っていた文承根の画業が、新しい生命となって甦ることであろう。
彼は疑いなく、コンテンポラリーアートの先駆者の一人である。モノ派、モノクロ派の源流の中で忘れてはならない画家である。最近ではあるが、日本の美術界で七〇・八〇年代の作家の見直し論が興っている。一~二年前には文承根の作品が京都国立近代美術館、大阪国立国際美術館、千葉市立美術館で収蔵された。未確認であるが、ブルックリン美術館や京都市立美術館にも収蔵され、クラコワ(ポーランド)国際ビエンナーレや、香港での国際展に出品された作品が、彼の地に収蔵されているとも聞いている。生前には栃木県立美術館、そしてソウル国立現代美術館にも収蔵されたことは、我々の心に灯る光明ではなかろうか。
遺された文承根の作品は、その先駆性と天賦を現代美術史の中で、光とメッセージを発し続けることであろう。
「病状六尺」
画家・孫雅由(ソンアユ)(一九四九~二〇〇二)
〈依願〉
二〇〇五年八月一八日、韓国大田市の李在興アジア美術館長が我が家を訪れた。李承晩初代大統領が祖父に当たる方で、日本への入国は始めてであるという。今まで日本の歴史認識の問題で思うところがあり、入国の機会がなかったそうである。
用件は、アジア美術館コレクション展を光州市立美術館で開催する計画があり、私の記念室を貸して欲しいとの事であった。
話が済んで在日の美術について関心を示されたので、美術誌『美庵Bien』(二〇〇四/Vol.28)に掲載されている孫雅由を紹介した。その会話中に、奥さんである桜井和子さんからの郵便で、孫雅由の画集が送られてきた。なんという偶然か、私は、そのことに驚きを隠せなかった。
同封されていた書簡には
「お願いがあります。お知り合いの学芸員の方がおられましたら、ご紹介下さいませんか。私の希望としては、孫雅由の作品を何点か収蔵していただければ、寄付をしたいと思います」
という内容のものであった。その手紙には、何か訴えかけるものがあるように思われた。
〈御縁〉
孫雅由との御縁を語りたいと思う。
一九九九年秋、京都太秦の孫雅由のアトリエを訪れたことがあった。第三回二〇〇〇光州ビエンナーレを記念して開かれる河正雄コレクション『在日の人権展』への出品要請のためであった。
その時、孫雅由を『在日の人権展』に招待し、いつの日にか光州市立美術館の河正雄記念室で、孫雅由展を開きたいと提案した。私の提案を孫雅由は大変喜び、『在日の人権展』の時には光州市立美術館で会いましょうと約束を交わした。
二〇〇〇年二月二日、大阪府立現代美術センターで開かれる『孫雅由展』の招待状が届き、大阪で再会する事となった。
その時、「交通費、滞在費、画材費など一切を負担するから、光州で滞在し新しい作品を製作、発表してもらいたい」
という、光州での孫雅由展の計画の案を具体的に提示し、内諾を得た。
そして二〇〇〇年三月二九日、光州市立美術館にて二〇〇〇光州ビエンナーレ記念『在日の人権展』が開催された。
開幕式に招待した孫雅由は、美術館の展示場の図面を要求され、
「三ヶ月ほど、光州に滞在して製作してみよう」
と意欲を示された。
ところが、その翌日、
「体調が悪いのでホテルの部屋で休みたい」
と言われた。食がない、下痢が止まらない、お灸をすえて欲しい、マッサージをして欲しいなど、同室していた私の息子の河洋樹に頼んでいたようだ。
薬や、精がつくようにと鮑のおかゆなどを差し入れしたりしたが、数日経っても一向に回復の兆しがあらわれないので、私はやむなく国立全南大学付属病院に入院の手続きをとった。だが、明日にでも京都に帰りたいという願いを聞き入れ、孫雅由は帰途に着いた。
それから二ヶ月も経った頃、息子宛に元気になったという便りがあり、二〇〇一年に福岡県立美術館で開かれる孫雅由展の案内があった。息子と共に、本当に元気になったのかなと語りあった翌二〇〇二年、報道で孫雅由が亡くなったことを知らされた。私は、孫雅由と親密な関係を築いていたわけでもない。共に語りあい、未来への展望へと約束しあった思い出は鮮明に残ってはいたが、孫雅由との御縁は、ここで断ち切られたものと思っていた。
だから、桜井和子さんからの手紙に、少なからぬ戸惑いがあったことは事実ではあるが、台風一四号の嵐の中、取り急ぎ京都に出向いた。
〈桜井和子さんの述懐〉
二〇〇五年九月七日、東山の智積院や泉涌寺に隣接する〈今熊野〉のバス停で、桜井和子さんと始めてお目にかかった。近くに大石内蔵助の腰掛石があるという滑り石街道(別名・山科街道)の脇道に入った、奥まったところにある自宅に案内され、桜井さんは語り始めた。
「三歳の頃から教会に通っていて、そこで辛い事の半分、重荷の半分はキリストが背負っているという説教を聞いていました。孫が鬱状態で、一日中同じ場所にじっと座っている日々が続いて悩んでいる時に、娘が強迫神経症にかかり、とてもしんどい日々が続きました。出来れば荷の全部をキリストに持ってもらいたい思いと、コーラスで気を紛らわすため洗礼を受けることにしました。二〇〇一年、立会人として京都本町ナザレン教会に孫を連れて行きました。
三ヶ月後に、梅宮義信牧師を信じる事が出来ると言って、孫も洗礼を受けました。プロテスタントであるため洗礼名はありません。孫は癌であることが判ってから、薬を飲んでも眠ることが出来ない辛い日々が続いておりました。洗礼を受けてからは、不思議なほど寝られるようになり楽になったと言いました。
でも孫は、クリスチャンでありながら、キリストを裏切っていたと思うのです。亡くなる少し前に、私の預金通帳から「少し使った」と他人に漏らしていたのを伝え聞いたのは、葬式が終わって三日目のことです。アトリエの家賃の精算に使われた様でもありますが、二〇〇万円ほどが下ろされておりました。そのお金で馬券でも当てて、今までの金銭上の精算をしておいてくれたら、そして、せめて一言「ごめんね」と生前に謝ってくれていればよかったのに、と思うと悔しいですね。
孫は遺言でエーゲ海に散骨してくれと言っていたので、二〇〇四年イタリアに行き、川に撒いたらエーゲ海に注ぐであろうと、流す川を探しました。運悪く川は干上がって水がなかったので、バチカンのサンピエトロ広場の噴水に散骨しました。ローマ法王の下で心を入れ替えて修行を積み、良きキリストの弟子になって貰いたいと言う思いから、そこに決めました。
もう一つは、隣接するバチカン美術館にはミケランジェロ、ラファエロ、ダビンチらルネッサンスの巨匠の絵があるので、これらの天才の隣にいる事が出来たら幸せなのではないか、とも思ったからです。
孫が鬱病であると気づいたのは、結婚した時の一九七九年です。孫の妹さんから
「和子さんがいるからお兄さんも安心やなぁ」
と言われたのでおかしいなあと思ったのは、今思えばこのことだったのでしょう。
私は父・桜井正身、母・シズエの一人娘として尼崎生まれですが、本籍は京都祇園町です。京都市立芸術大学造形科を出て、豊中の中学で美術を教えている一九七九年頃、西宮の版画工房で孫と知り合いました。その時、孫は水中生物の印象を受けるドライポイントの小作品を製作しており、私も同じような抽象的な作品を作っていました。
結婚してから鉛筆で描く作品を始めましたが、全然売れませんでした。半年に一枚売れる程度で、二万円ほどの収入しかありませんでした。その時は孫は精力的に作品を製作し、売り歩いておりました。私の年収は二〇〇万円ほどでしたので、孫を支えることが出来ました。
結婚の際、神戸の先の三木で大衆食堂を経営していた孫の父が、家財道具でも買うようにと二〇〇万円をくれました。孫はそのお金を半分ずつ分けようと言っていましたが、結局全部酒代として使い果たしてしまいました。孫は酒を飲んで家には帰らなかったことが多く、最初は気づきませんでした。
結婚してから、孫の言動が飲んでいない時も攻撃的で、ダラダラと生活するようになり、アルコール依存症であることがはっきり判ったのは、一〇年も経ってからのことです。アルコールを飲まなくなると鬱病、自立神経失調症を繰り返しておりました。
ドア一枚中に入った途端に性格が変わるという具合で、外で機嫌良くやっているのが辛いようでした。そんな私達の状況を見かねてか、孫の父母や通産省の研究所に勤めていた私の父が、間接的に支えてくれるようになりました。この家も父が買ってくれたものです。
一九九六年、孫は自分から一度だけ病院に行った事がありました。その時は、アルコール依存症のグループカウンセラーを受けたのですが、自分は絵描きだから、もう行かないといってそれきり、病院には行きませんでした。その時の検査の結果、肝臓が悪くなかったからだと理由付けていました。
その頃、中島らもさんがTVで
「女の人のろくろ首が見える」
という幻覚の話をしているのを聞いて、
「自分もそういう幻覚を良く見る」
と言ったことがあります。
孫は自分以外の人間は判らないし、信じられない、付き合わないといった全く融通性のない、世間を知らない人でした。自分の作品だけに執着する精神構造で、人格と行動においては、作品と別であるかのように振る舞った人でした。芸術家にはよくある性質なのでしょうかね。
一九九七年から一九九八年までの一年間、イギリスに滞在している時に、体調を悪くしました。一九九八年に大腸癌が見つかり、腸閉塞で、すぐにでも手術を受ければよかったものを、病院に行くのが怖かったのでしょうか、二〇〇一年になって京都の日赤で手術をした時には既に肺、肝臓、リンパ腺、腹膜などに癌が転移しており、余命六ヶ月との宣告を受けました。事実、お医者さんの言う通り、六ヵ月後に亡くなりました。宣告された時は、本人も相当に堪えたようで、かなり落ち込んでいました。
体力が落ちるからと言って、抗癌剤や放射線治療は一切せず、近所の病院で栄養剤の点滴を受けることしかしませんでした。
作品は完成しているから、作品のサインや美術館に収蔵するために整理することだけだと言って、亡くなる直前まで、その作業に没頭しておりました。
亡くなる前日、風呂に入りたいと風呂場に入ったところ、右腕が利かないと言ってから意識を無くし、救急車で京都第二医療生協病院に入院しましたが、翌日の二〇〇二年二月二一日に亡くなりました」
淡々と忌憚なく語る話の内容に、私は相槌を繰り返すばかりで、孫雅由の実生活の生々しい実情と、彼の作品世界とのギャップにただ驚くばかりであった。
〈闘病の日々〉
正岡子規(一八六七年~一九〇二年)の晩年、脊椎カリエスの闘病生活は壮絶であったという。
「絶叫。号泣。その苦、その痛、何とも形容することは出来ない。誰かこの苦を助けてくれるものはあるまいか」(『病牀六尺』岩波文庫)
そんな声がしてくるような話であった。それは病と闘う本人だけでなく、飽くなき芸術への欲求のために、その家族にも言える闘う地獄なのではないかと思った。
しかし極限状況の中で生み出された作品からは、六ヶ月の余命と宣告されてから、死の直前まで作品に向き合って整理をしていった孫雅由の境地に、私は無限の慈愛を感じる。
〈収蔵〉
孫雅由の作品は、多くの美術館に収蔵されていることを桜井さんから知らされた。
記録によると
① 二〇〇一年 福岡アジア美術館 一三点
② 二〇〇一年 伊丹市立美術館 二八七点
③ 二〇〇二年 宇都宮美術館 四点
④ 二〇〇二年 福岡県立美術館 七九点
⑤ 二〇〇二年 国立国際美術館 四点
⑥ 二〇〇二年 京都国立近代美術館 三点
⑦ 二〇〇三年 兵庫県立美術館 二点
⑧ 二〇〇四年 和歌山県立美術館 四七点
⑨ 二〇〇四年 東京都現代美術館 一点
⑩ 二〇〇四年 徳島県立近代美術館 一四点
である。
死の宣告を受けて、孫雅由自身が身辺の整理をし、作品を美術館に収蔵するために生前に手続きを取ったのは福岡アジア美術館、伊丹市立美術館、宇都宮美術館であった。
寄付理由を
「朝鮮半島に古くから流れる美の源流が我々、在日のアーティストが持っていること、そして、その美に触れて頂きたく寄付をします」
と本人自ら記してあるものを見て、朝鮮半島と在日の狭間に生きる血を意識している孫を愛しく思った。
〈出自〉
孫雅由の略歴は別記で紹介するが、その略歴によると一九四九年九月一六日大阪曽根崎にて在日韓国人二世として生まれたとある。
本籍簿によると、慶尚北道迎日郡(現・浦項市南区)東海面イムゴッ里五九二番地にて父・孫洙翼(本貫・慶州)、母・張乙俊との間に、兄と弟三人と妹二人の七人兄弟の次男として生まれたと記載されていた。
私も布施市(現東大阪市)の生まれだが、本籍地には全羅南道霊岩郡出生となっているように、在日韓国人は父母の本籍地を出生地として載せている。孫雅由も同様であった。
二つの祖国、二つの故郷の出自を誇り高く胸に抱いて、孫雅由もまた在日を生きた記録が戸籍簿にはあった。
作品『色の位置』には、唐辛子の赤色を連想させる民族的な色彩を使っている。そこから出自〈族譜〉が根幹にあることは、孫雅由の行動や作品に投影されていることを感じ取ることが出来ると思う。
孫雅由の作品からは、色々なジャンルの音楽がグローバルに協奏しているイメージがある。厳粛なクラシックもあれば、陽気で軽快なラテンやジャズ、洒落たシャンソンや哀惜漂うパンソリもあるというように、複雑に色が音楽のように共鳴しあっている。リズミカルで伸びやかな線の動きが自由に歌い、豊潤な色彩がハーモニーとなり平安を奏でている。
孫雅由には、音楽のセンスを感じることはなかったと桜井和子さんは語ったが、閉ざされた心の中で孤独を紛らわすために、孫雅由は作品により〈協奏曲〉を作曲し奏でていたのかもしれない。
残された作品は、桜井和子さんが孫雅由の遺志を継いで、各美術館に寄附収蔵したものである。この作業は、孫雅由の生の証であり死して尚、美術活動の終着点を目指す執念であると思う。
この努力により、次の世代に孫雅由の存在を記憶される事は間違いないことで、必ずや孫雅由は作家として祝福を受けるものであると思う。それは遺志を継いで、収蔵に尽力される遺族に対してもそうだと私は思う。
〈画論〉
以下は私が読んだ孫雅由の主なる画論である。
『絵画の根源から出る、視覚的実験 福岡市美術館学芸員・山口洋三』
『関係する線-孫雅由作品集に寄せて 手塚山学院大学美術史教授・島本浣』
『立ち現れる線と色 孫雅由の世界・師子堂恵信』
『“孫の絵画の身体性”・“精神の〈場〉としての風景-孫雅由の絵画について”
国立国際美術館主任研究官・中井康之』
「光と大気 大阪府立現代美術センター学芸員・小口斉子」
どの画論も、孫雅由の美術世界を理解するのに助けになっている。『光と大気』の文末に“予響曲・コバルトブルー&イエロー”の作品について
「孫はこれらの作品を、自己の癒しの為に描いたと語ったが、その作品によって我々もまた、自己の存在を確認し、癒されるのである」
という文が、私には身近に感じられた。これらは生の終局を燃やし、死の旅立ちの世界を見続けていたような作品であり、孫雅由が到達した美術世界の終着を暗示させ、生の感動をもって表現をしている。『泥中に一蓮華』と言える静謐な作品を残されたことは、福音ではなかろうか。
〈もの派〉
今、石や木、紙や綿、鉄版やパラフィンといった『もの』を素材に、物質や物体を直接的に提示した表現を作品としていた『もの派』が韓日の美術界で再考されているが、美術を志した出発点において『もの派』の高山登(一九四四~)に師事したことで、孫が求めた美術世界は形成されたように思われる。
高山登は、二〇〇〇光州ビエンナーレで光州市立美術館の前庭に枕木を使った作品を出品し、孫雅由は、同美術館において『在日の人権展』に“空間の間合い”の作品を展示し、師弟が奇しくも出会うこととなった。
高山登の父は、戦前に朝鮮から日本に渡って来た治金技術者であった。近代化、国家、アジア、民族、戦争とは、民族的な出自から反時代的に問う「枕木」の立体作品には、力強く訴えるものがあった。
孫雅由の作品は郭仁植、李禹煥、文承根と受け継がれた表現様式『もの派』の源流から、自己の表現を試みた作家であることを確認させるものであった。
何故か、高山も孫雅由も生とも死とも直結している、異界への入口を連想させる痕跡の対比をもって、過去をも連想させる作品があるのは、死生観を共有しているのではないかと恨(ハン)深い世界を私は感じるのである。
孫雅由の絶作“予響曲・コバルトブルー&イエロー”は、メッセージとして、それらのことを語っているように思えてならない。
〈コレクション〉
私は、孫雅由に対する色々な想いから京都に三度出向き、そして桜井和子さんと会った。作品を整理し話を進めるうちに、孫雅由はなんと幸運な作家であったのかと思うようになった。
彼は桜井和子さんの話によれば、決して品行方正ではないし、善人とはいえない。普通の人が眉をひそめるような、一般人とは違う価値観でものを見て行動し、全霊を幾重にも重ねられた芸術の創造に捧げて生きたからだ。
肉体は滅びても、作家には作品が残る。それは、その作家の肉体と精神の分身ともいえるものであり、死してなお生き続ける。それは祝福でもあるのではないか。
孫雅由は父母に恵まれ、妻に恵まれ、子は二女に恵まれた。俗ではあるが、周囲の愛すべき人材に支えられた恵まれた人である。
そして、自らの血肉である作品が、日本の著名なる美術館に収蔵されたことは、在日作家としては稀な事であり、評価を受けることは恵まれたことだと思う。
作家として自分は一番であると、周囲を気にもせずに芸術活動一筋に駆け抜けていった。周囲に苦労も恨(ハン)も振り撒くのも構わず、芸術家として誇り高く一人良く生きたといえるのではないか。
李在興アジア美術館館長は
「早逝は、何も作家にとって損失ではない。ボロが出ないうちに去ったことが、ラッキーな作家もいる」
と語った。なんと皮肉で、しかし含蓄のある言葉ではないだろうか。そして
「これからは日本を知るため、在日を知るため、年に一度は必ず河さんを訪ねる」
と付け加えた。
こうして残された作品一七四点は、河正雄コレクションに収蔵されることとなった。
祖国の光州市立美術館に、河正雄コレクションとして新たに在日作家孫雅由の名が永遠に記録され、愛されることになるであろう。
この収蔵にあたり、寄贈者の桜井和子さん、そして資料を提供して下さった〈アートスペース虹〉のオーナー熊谷寿美子さんに心から感謝する。
〈孫雅由 略歴 SON AH-YOO〉
一九四九 大阪曾根崎にて在日韓国人二世として生まれる
一九六六 美術家を志し上京、高山登の教えを受ける
一九六八 多摩美術大学入学、そして自主退学
一九七五 ドイツ留学のため一時帰阪するが、アクシデントがあり渡独を断念。
その後、父親の仕事を一時手伝う
一九七六 兵庫県宝塚の山中に小さな小屋をアトリエにして『現前』シリーズを制作する
一九七八 始めて祖国韓国の土を踏み、李氏朝鮮朝の王宮・景福宮の石組みを見る
一九八〇 兵庫県西宮に、工房イュプシロンを設立し、アートプロデュースを開姶する
一九九四 京都東山に住居を移す
一九九五 阪神大震災により、工房イュプシロン全壊
一九九六 京都太秦にアトリエを移す
一九九七~九八 スコットランド、エジンバラに人智学研究のため留学
二〇〇二 二月二一日死去
パブリック コレクション
イビザ現代美術館(スペイン)
フレデリクシュタット美術館(ノルウェー)
プティオーマ美術館(ベルギー)
J・ダラビー・ギャラリー(ロスアンジェルス/USA)
大英博物館(ロンドン/英国)
ノルウェー現代版画美術館(ノルウェー)
エスタンプコレ(ルクセンブルグ)
元庫文化財団(ソウル/韓国)
ギザ王立アートセンター(エジプト)
ウクライナ国立美術館
Pdnshwowd Galeria Sztuki(ポーランド)
スロベニヤインターナショナルクラブコレクション(スロベニヤ)
ベルリン市ダッチインターナショナル美術館(オランダ)
大阪府立現代美術センター
光州市立美術館(韓国)
ワルシャワ国立美術館(ポーランド)
福岡アジア美術館
福岡県立美術館
伊丹市美術館
兵庫県立美術館
和歌山県立美術館
国立国際美術館
京都国立近代美術館
宇都宮美術館
東京都現代美術館
徳島県立近代美術館
「日本の友よ、さようなら」
画家・曺良奎(チョヤンギュ)(一九二八~不明)
〈接点〉
今、曺良奎の仕事について、韓国と日本の美術界での評価が高まっている。韓国で近代美術史学会が創立されたのは一九九三年、北に渡った美術家達が解禁されたのは一九八八年からである。不幸な過去を乗り越え、近代美術を見直そうと省察の時を迎えたのである。戦後、在日コリアンの美術が韓日の美術史の中で評価されず、研究も殆どされてこなかった。無関心の中忘れられ失われ、顧みられなかったのは政治的、歴史的なことで制約を受け、南北の分断そのものが理由であったのは不幸としか言いようがない。
「七〇年代以降の日本の美術は、例外もあるが社会的主題を喪失してしまった。曺良奎の作品を除くと、日本の戦後美術史は重要な一角を欠くこととなる。社会への矛盾と軋轢を絵画を通し、自分の主張として表していったのが曺良奎であった」
針生一郎氏は、曺良奎をそう評価している。
韓国の美術研究家・尹凡牟(ユンボンモ)著『美術と共に社会と共に』(一九九一年美真社刊)が発刊され、『分断の時代と曺良奎の美術世界』という一章がある。「理念の葛藤と南北分断の犠牲となった“資本主義の中での疎外”を素材として、日本で頭角を表した悲運の画家」と中央日報で報道されたことで、一九二八年一二月一五日生・慶尚南道陜川出身の曺良奎(チョヤンギュ)は、広く韓国で知られ注目されるようになった。
〈出会い〉
一九九八年、国立徳寿宮美術館開館記念『近代を見る目・再び捜し出された近代美術展』に、私のコレクションから在外同胞の作家として全和凰、宋英玉と曺良奎が選ばれ出品した。人々の記憶から忘却されつつある朝鮮半島の画家達の作品、海外を放浪した画家達に光が当てられ、韓国近代美術史の再評価の課題を捜し出し、新しい発掘の成果を示した展示となった。この記念展は、再び徳寿宮で美術館を開館したことと相まって、象徴的な意味を持っている。
世界美術界における、コンテンポラリーアートの主流に押し流された反省を基にした近現代作品の見直しと、再評価に目を向け始めたのである。ここにその意味を加えるために、これまで公開できなかった有・無名作家達の近代期作品、個人に収蔵され一般公開されなかった一四六点が公開された。近代美術史の筋を正し、歴史観と美学的観点を再確立しようという意味から開催されたのだった。また同年日本では、名古屋市美術館で『戦後日本のリアリズム展』において、私のコレクション内から寄贈された京都市立美術館蔵、全和凰作『ある日の夢(銃殺)』と曺良奎『一五番倉庫』『マンホールB』(いずれも宮城県美術館蔵)が展示され注目を受けた。日韓の美術界で、在日の美術の存在が大きくクローズアップされたのである。
〈逃亡〉
曺良奎が絵の勉強を始めたのは一九四五年八月一五日以降、日本が終戦を迎えた後である。日本の敗戦を軸に開放感と同時に、虚脱感に打ちひしがれていた時である。絵画と政治の一致を求め、政治運動に身を挺したが過酷な現実状況に耐えられず、逃亡への道を選び日本に来たのだ。追われる者の心情は侘びしく悲しいものである。
一九五四年秋、曺良奎が李承晩政権下の官憲による逮捕を逃れるため、危険な日本への密航を決意するまでの経緯を語る。
朝鮮半島は一九四六年八月に朝鮮労働党、一一月には南で南朝鮮労働党が成立した。曺良奎は、一九四六年七月一五日普州師範学校(現普州教育大学)尋常科三期生として卒業し、同年九月頃に釜山土城公立国民学校に教師として赴任した。学校の養護室で自炊生活を送り、その頃抽象画をよく描いていたという。一九四七年春、南労党は非合法化され、曺良奎は画学生ということで追求を逃れていたが、同年八月の夏休みの時、国旗掲揚台に教え子の五年在学生の申明均に命じて北朝鮮人民共和国旗を掲揚させたことで、曺良奎は南労党員だとマークされ、警察に追われる身となってしまった。
一九四七年真冬のこと。母とオンドル部屋で寝ていたところ、一〇人近い武装警官に家の周囲を取り囲まれたが、台所の裏口から奇跡的に脱出した。山を越え、普州からそう遠くない蛇虎島で、母の親戚宅の牛小屋の天井裏に四ヶ月間隠れていた。後に日本で描いた、牛を題材とした『牧童・一九五三年』は、一九五四年アンデパンダン展出品作品で、この時観察した牛のイメージであるという。
しかし追求の手が廻り、船便で釜山に逃げ、師範学校時代の同僚の世話で、再び土城国民学校に潜り込み教員生活に戻ったのだが、危険を知り、一九四八年秋、和船で九州の鷹島に逃げた。
そして日本にいた普州師範学校の同期生の助けを受けて、深川枝川町の朝鮮人部落に辿り着く。そこでは日本共産党の入党を拒否、石川島造船所と近所の倉庫で同胞人夫と共に働いた。一週間に三日働いて四日研究所に通う生活を送る。傷だらけの心情のままに、敗戦日本の社会状況の中に放り込まれ、東京の町をあてもなく彷徨い、体験により自己の肉体を確かめうる実感をもって、自己回復への渇望に喘いでいた。
〈出発〉
曺良奎は、一九五〇年に起きた朝鮮戦争により、皮膚感覚で民族の危機を受け止めた。一九五二年武蔵野美術学校を中退して、『朝鮮に平和を』油絵三〇号と枝川町朝鮮人部落のデッサン二〇枚を出品、日本アンデパンダン展と自由美術展に発表したのが日本で美術家としての出発となる。
一九五三年、朝鮮戦争が休戦となり、自らを育んでくれた祖国の山河を強く浮かべ、夢想しながら『牧童』を描いた。滝口修造の紹介により、神田タケミヤ画廊にて第一回個展、そして具象展や四三人展、四六人展に参加。倉庫シリーズに入る変革に至るまでには、様々な屈折を経た。
『凶作』(一九五三年)、『目立て』(一九五三年)、『花を持つ男』(一九五三年)、『土地を奪われる』(一九五五年)などは、状況の混乱に耐えていこうとする曺良奎自身の意志を容体化してみたものである。
〈倉庫・マンホール〉
『倉庫』は、曺良奎の住んでいた身近な情景から誕生した。生産の現場ではなく、集積過程の機構を描くことで、人間との不条理な分離を試みたのである。
『三一番倉庫』(一九五三年・河正雄コレクション)『首を切られたにわとり』(一九五三年・河正雄コレクション)『L倉庫』(一九五七年)『密閉せる倉庫』(一九五七年・東京国立近代美術館蔵)と製作が進む中、次第にその対立葛藤を明確にし始める。何ヶ月か後には『人足と倉庫』(一九五七年)アンデパンダン展出品、『倉庫』(一九五七年)と一連の『倉庫』シリーズ製作を終えた。
曺良奎はその過程を整理する中で、資本主義社会の暗黒面の象徴としてのモチーフに〈マンホール〉を選んだ。毎日私達がその上を歩き、誰もが知っていながら、そこに人間的意味を感じ取れないものに製作的興味を移行した。倉庫の立面からマンホールの平面へ、状況の中で息づいている下層労働階級の暗黒面と、生への渇望を暗示的に画面に盛り込んでいった。状況に落ち込んでいる客観的人物像と、その状況下からの脱出のエネルギーをダブらせて、状況を乗り越えうる典型的な人物を表現する。
『マンホールA』(一九五八年)、『マンホールB』(一九五八年第二回安井賞候補新人展出品・宮城県美術館蔵)、『マンホールC』(一九五九年村松画廊第二回個人展)へと至る。『マンホールD』(一九五八年第三回安井賞候補新人展出品)、『マンホールE』(一九五八年アンデパンダン展出品)では、具体的状況を見つめる作家の内的表現の可能性を探った。『マンホールC』は、一九五九年に読売ベストスリーに選出された。一九六〇年、みづえ賞選抜展に『仮面をとれ』を出品する。
〈平和獲得の戦い〉
曺良奎は『マンホール』一連の作品を描きながら、自分が日本の現実の中に入り込んでいく程に資本主義体制の諸矛盾に悩みを抱くが、日本で得た創作の経験を通して、創作の意味を形作る自信を得ていった。しかし、曺良奎の中に、南北分断に対する思いが日増しに強くなっていく。
「南北が分裂しては、朝鮮に平和は有り得ない。その平和獲得の戦いこそ、創作に関わり合う表現者としての任務である。日本での貴重な体験こそが、私の中で強く生き続ける。リアリティがある限り、リアリズム絵画に囚われなくても良いのだ」
関根正二を愛し、フォートリエに共感を寄せ、観念の絵を描いて、日常的に関わり合った日本との関係はこれで切れた。
「日本を去るに至り、少年時代の記憶に戻る。日本の友よさようなら」
日本で実力を認められ、仲間からも一目置かれる存在になり、私をも含む自由美術出品者らの憧れの人。曺良奎はそう言い残して北朝鮮へと渡る。いろいろと解決しなければならない問題をはらんだままに。
〈憧れ〉
私が、曺良奎の作品と足跡に興味を持った経緯を語りたい。
私は一九五九年三月七日、秋田工業高校の卒業式を終えたその日、上野行きの夜行列車に乗って上京した。卒業証書と身の回りの物を入れた通学鞄一つが、私の所持品だった。画家になる夢を抱えて、秋田での一八年間の生活に別れを告げた。
目黒の柿の木坂に下宿し、武蔵小山にある明工社という配線機器製造メーカーに務めた。昼は配線機器の設計の仕事をして、夜は代々木にある日本デザインスクールに通い、商業デザインの勉強をした。数ヶ月後に、川口の芝川沿いにマッチ箱のような家を購入して、そこから明工社に通った。朝五時半には家を出て、帰宅は夜の一〇時半過ぎであった。
そんな頃に曺良奎が北朝鮮に帰国する。一九六〇年一〇月七日に、新潟から北朝鮮に渡ったと報道で知った。その年の一二月になって私は目を痛めてしまい、三ヶ月ほど入院し、盲目での生活を余儀なくされた。過労と栄養失調から来る障害であったのだが、運良く回復することが出来た。その事で会社も学校も辞めざるを得なくなってしまう。
一九六一年九月、台風の水害により、我が家は水没した。その時、川口の朝鮮総連の人達がボートに乗って慰問に現れ、お米を配給してくれた。その人達から、北朝鮮は天国のような所であるという事を聞き、行き場を無くし悶々としていた時だったので、私も曺良奎のように北朝鮮に行き、絵の勉強をしようと総連事務所に行ったのだった。しかし
「少し北に行くのは保留して、君はこの総連事務所の仕事をしてもらいたい」
と慰留され、そこへ務めることとなった。今考えると、このことが私の人生の大きな分岐点になるのだが、その頃の私に判ろう筈もない。
しばらくして当時、戸田市に住んでいた画家の許勲氏が事務所に私を訪ねてきて、在日本朝鮮文学芸術家同盟(文芸同)に入らないかと誘った。文芸同に入会したことで、在日同胞作家と美術世界を知る接点が出来た。そこで、文芸同の会員であった曺良奎についての情報も多く得ることが出来た。曺良奎との直接の出会いこそなかったものの、こんな時代背景と伏線が曺良奎を気に留める存在にし、今なお継続しているのである。
〈対話〉
マンホールの作品に至るまでの、曺良奎の言葉である。
「人間が自己の労働に誇りと尊厳を持ち得ず、ただ最低に生きるためにのみ働かざるを得ない社会機構。自己が経験し、周りの労働者から受けた偽りのない実感である。具体的対象物の認識を、具体的生活感情による理念の論理構造に基づいて、それを感情構造に高めうる時、現実認識としてのリアリズムが確立すると思う。芸術家が政治的、社会的状況に無関心な状態で芸術の意味がよりよく成立するという意識の破壊こそ、新しい芸術への道であり、それを具体的交感に基づいて積み重ねていかねばならないのだ」
マンホールや人物の表情と画面の緊張感から、何が美しく見えるのか。優しく微笑みかけてくるものよりは、激しい敵意と反撥を感じさせるものの中に対話を求めた、重くて力強いリアリズム。「対話」、これこそ作品から受ける曺良奎の芸術の本質ではないだろうか。
激動する解放後の朝鮮半島と日本の社会状況の中、日帝後期時代に青春を過ごした在日朝鮮人の知識人は、全ての既成的な価値観が崩壊しつつある中で、共通した模索をし続けた。それぞれの画家が、生きてきた時間や民族の記憶に根を下ろし、『時代の証言』とは現在、そして未来に語り継がれていくのはどの様な記憶なのか。等しく真摯な絵画製作に情熱を燃やしたのが、この時代なのである。
〈コレクション〉
曺良奎作品を、コレクションする事となった経緯を語る。
曺良奎の作品をコレクションすることを、早くから熱心に薦めてくれたのは李禹煥、宋英玉であった。その助言を頼りに数年間、捜してみたのだが情報はなかなか入らなかった。一九八五年になって、洲之内徹(一九一三年~一九八七年)のコレクションの中に、『マンホール作品B』があるという情報を得て、洲之内が経営する銀座六丁目の〈現代画廊〉を訪ねた。私はすぐさま交渉したところ
「三〇〇万円なら売りましょう」
と答えたので、家に帰り次第送金すると約束してわかれた。しかし、家に着いた頃に洲之内から
「申し訳ないが売るのは辞めます。その作品は、いずれ美術館に寄贈しようと思っているのです」
と断りの電話が入った。私は
「美術館に入れるということなら、曺良奎も喜ぶでしょう」
と諦め了承した。洲之内の死後、この作品は宮城県美術館へ洲之内徹コレクションとして寄贈された。
それから数年が経った頃、銀座の画廊〈七七ギャラリー〉から、『倉庫一三番』が売りに出たと報せを受けて即購入した。間もなく『首を切られたにわとり』があるというので、価格の交渉に入った。しかし、余りにも高額だったために交渉は行き詰まり、そうこうしている内に作品所有者が売るのを辞めてしまった。その絵との縁が切れた数年後、そういうことも忘れてしまった頃に、遺族が再びその作品を売りに出したので、どうかという打診があり、即購入を決めコレクションにした。
水彩画『倉庫番』(一九五六年)の作品は、針生一郎氏のコレクションであった。ある講演会で、針生一郎氏が曺良奎が北朝鮮に渡った後に葉書を送ってきたという話をした。私は、その葉書の原本を見たいと針生氏に頼んだ。針生氏は書斉や本棚を捜してくれたのだが、その葉書は出てこなかったという。しかし代わりに、曺良奎が北に帰る際に出版した画集に、針生氏が文を寄稿したお礼にとくれた水彩画『倉庫番』が出てきたと言った。針生氏は、その作品を河正雄コレクションに寄贈してくれたのである。
このようにして、曺良奎作品三点が河正雄コレクションとなった。それらの作品は『再び捜し出した近代美術展』(国立徳寿宮美術館一九九八年一二月一日~一九九九年三月三一日)、『祈りの美術展』(光州市立美術館一九九九年一一月三日~一一月三〇日)、『在日の人権展』(光州市立美術館二〇〇〇年三月二九日~六月七日)で公開され、韓国の美術界に鮮烈に印象づけられたのである。
〈悲運の作家〉
曺良奎は
「日本の戦後、特に朝鮮戦争以後の社会状況の中に生きた一人の朝鮮人が、独占資本主義的社会体制の中に生きる現代人としての対象認識を通して、思想の模索を続けた過程であります。過去の日帝時代に、植民地化の朝鮮に生まれ、その支配からの脱出と同時に、新しい強暴な支配者の手元に墜ちていく、南の社会政治情勢下にあって、逃亡という方法を余儀なく選び、それ故につまずきへの、深い屈辱感に苛まれながら、新しい思想の論理を築こうと渇望した時期であります」
という言葉を残して北に渡った。渡ったところで思想、政治的軋轢から解放されるかも、ましてや絵が描けるかどうかも定かでないのに、枝川で知り合った妻と二人の子供と共に北の祖国に幸福を求め、消息を断った悲運の画家であった。一九六〇年一〇月七日、日本と別離してから今現在、曺良奎の消息は深い闇の中にある。
「再び探し出した近代美術展」を見る
〈徳寿宮美術館再オープン〉
木枯らしに木の葉が舞う一九九八年一二月一日、ソウル・徳寿宮で金鍾泌首相、申楽均文化観光部長官を迎えて開かれた徳寿宮美術館再オープン式には、内外の芸術関係者五〇〇人余りが集まった。
徳寿宮石造殿は美術との縁が深い。一九三七年建築され、解放後は国立中央博物館、国立現代美術館として使用されたことで、徳寿宮といえば美術館というほど親しまれた。その後、宮中遺物展示館となったが、このたび西館が国立現代美術館分館として一〇年ぶりに蘇ったのである。
開館記念展は『再び探し出した近代美術』展(一九九九年三月三一日までの会期)であるが、この記念展は再び徳寿宮で美術館を開館したことと相まって、象徴的な意味を持っている。世界美術界におけるコンテンポラリーアートの、主流に押し流された反省を基にした近現代作品の見直しと、再評価に目を向け始めたのである。ここにその意味を加えるために、これまで公開できなかった有・無名作家たちの近代期作品、個人に収蔵され一般公開できなかった一四六点の作品を公開することになった。わが近代美術史の筋を正し、われらの歴史観と美学的観点を再確立しようとする意味から、開催された美術展は世紀末の必然と思いたい。
一四六点の出品のうち、在外同胞の作品としては一四点の油絵が展示されたが、在日からは私のコレクションから全和凰、宋英玉、曺良奎の油絵各二点ずつ、六点が出品された。この六点の展示は在日の存在感を示す作品として、関心度が高かった。出品された三人の作品と作家を紹介したい。
〈作品と作家の紹介〉
私が在日作家の作品のコレクションを始めた因縁深い作家は、全和凰(一九〇九~一九九六 本名は鳳済)である。平南安州出身で、平壌崇仁中学を中退後、一九三一年朝鮮美術展で入選、東亜日報や朝鮮日報などに童画を発表した。一九三九年、京都の一燈園に入園、そこで京都画壇の大父須田国太郎と出会い、日本で本格的に画家として活動を開始。一九四七年、『光泉林風景』で京展賞、五一年、『群像』で行動美術賞を受賞した。一九六三年の画業三〇年展と八二年の画業五〇年展は、私が主催して、東京、京都、ソウル、大邱、光州と巡回展を行い、前後七年の歳月をかけて画集も出版した。
画風は『祈りの芸術』と評され、宗教的精神性と詩情と風土性、ヒューマニティーにあふれた作品を発表してきた。
本展には『光泉林風景』と『ランプ』(一九四七)の二点を出品、時代の臨場感ひしひしたるものがその作品世界だ。一九九三年、光州市立美術館に作品九二点が収蔵・展示された。
宋英玉(一九一七~一九九九)は済州島出身で、小学校四年の時日本に渡ってきた。大阪中之島洋画所を経て、太平洋戦争真っ最中の一九四四年、大阪美術学校本科を出た。五〇年代は日本アンデパンダン展(一九五六~一九六〇)を舞台に活躍し、自由美術展で平和賞を受賞した。一九八三年、母国訪問団の一員として五五年ぶりに帰郷し、祖国でも交流展で作品を発表した。
宋英玉には、歴史の暗部を黙示する告発の作品が多い。彷徨の自画像とも言える『犬』三シリーズには、反抗と生命の躍動感がある。本展の出品作は『廃船』(一九六一)と『女手品師』(一九六〇)である。
不世出の英才・曺良奎が、慈父と慕った面目を感じさせる作家である。光州市立美術館には、彼の作品一七点が収蔵展示され、三〇点の追加収蔵が予定されている。
曺良奎(一九二八~?)は、慶尚南道晋州に生まれた。一九四七年、晋州師範学校を卒業後、釜山で国民学校の教師をしていた時、社会運動に関わり、警察の弾圧、捜査から逃れて日本に密航した。一九五二年、武蔵野美術学校を中退し、同年日本アンテバンダン展に『朝鮮に平和を!』初出品した。翌年、日本で初個展を開く。
一九五五年、自由美術家協会会員になってから、第二回安井賞候補(一九五八)、第三回安井賞候補(一九五九)に選ばれて、読売ベストスリーに選出される。一九六〇年、みずゑ賞選抜展に出品、その年に美術出版社から『曺良奎画集』を発刊し、注目された。その画集は、彼の北朝鮮行きの送別の記念画集である。針生一郎、滝口修造、中原佑介、野間宏、井上長三郎らは惜別の情をもって、この若き未完の天才に送別辞を送った。
日本で残した作品として分かっているのは三〇点余りで、東京国立美術館に『密閉せる倉庫』(一九六〇)、東京都美術館に『マンホールB』(一九五八)がそれぞれ収蔵されている。本展には『31番倉庫』(一九五五)と『殺されたニワトリ』(一九五五)の二点が出品された。『31番倉庫』には、日本で彼の「生」が『殺されたニワトリ』には、民族の悲劇としての痛ましさが血で描かれているように思える。この作品は、彼の将来を予測する悲劇そのものを暗示、黙示しているようでもある。
私は一九六〇年と六一年、日本アンデパンダン展に出品した経験があるが、日本アンデパンダン展での彼との出会いは、すれ違ったが、本展出品の二点が私のコレクションとして残された。
徳寿宮美術館の光復とも言える『再び探し出した近代美術』展の観覧を、是非お勧めしたい。